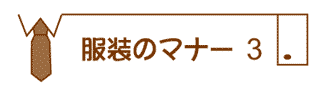
[冠婚葬祭の服装とは]
冠婚葬祭のさまざまなシーンにおける服装には、決まりがあります。このページでは冠婚葬祭のうち、冠=子供の成長を祝う儀式の服装のマナーについてご説明いたします。 子供の成長を祝うお祝いには、お宮参り、七五三、成人式などがあります。
| ………このページの内容……… | |
|---|---|
| ▼3.子供の成長を祝う儀式の服装 | |
| 3-1.お宮参りの服装 | |
| 3-2.七五三の服装 | |
| 3-3.成人式の服装 | |
| ↓ 下記は別ページ ↓ | |
| (▼1.婚礼の服装(結婚式・披露宴の服装)>>) | |
| 1-1.結納の服装>> | |
| 1-2.結婚式・披露宴の服装>> | |
| 1-3.二次会の服装>> | |
| (▼2.通夜、葬儀、法事の服装)>>) | |
| 2-1.お通夜.お葬式(葬儀)の服装>> | |
| 2-2.法事・法要の服装>> | |
| (▼4.入学式の服装)>>) | |
| 3.子供の成長を祝う儀式の服装 |
| 子供の成長を祝う儀式の代表的なものに、お宮参り、七五三、成人式があります。例えば大人になったことを祝う成人式は現代では二十歳で祝うものですが、もともと奈良時代以降は「元服」と呼ばれ男子が成人になる儀式であり、今よりもずっと若い11〜16歳くらいで行なわれるものでした。成人すると冠や烏帽子など頭につける(身分によって着用するものが異なる)ことから加冠とも言われたそうで、冠婚葬祭の冠はここから来ています。 現代では身分制度もなく、昔ほど成人の儀式の服装も厳しく決められているわけではありませんが、子供の成長を祝う代表的な儀式の服装のマナーをご紹介します。 |
| 3-1.お宮参りの服装 |
|
お宮参りは、赤ちゃんの誕生を祝い、氏神様に感謝をし健やかな成長を祈願する儀式です。初宮参りとも言われます。
もともとのしきたりでは、赤ちゃんとその両親、そして父方の祖母の4人でお参りするものです。父方の祖母が赤ちゃんを抱くのが正式なお宮参りのしかたなのですが、最近では両親と赤ちゃんの3人だけでお参りするケースも増えています。また、中には赤ちゃんの誕生を両家の祖父母も一緒になって皆が祝うという意味で総勢七名でお参りするご家族もいらっしゃるようで、次第にしきたりにはこだわらなくなってきました。 下記にご紹介するのはお宮参りの一般的な服装の例です。 |
| (1)お宮参りの際の赤ちゃんの服装 |
| ◎赤ちゃんが着るお祝い着は、正式には母方の実家が用意するものです。 ◎正式な祝い着を着用するご家庭もいらっしゃいますが、最近ではお宮参りは、その後も利用できるお洒落着で済ませ、記念写真撮影時のみレンタルの衣装を着用するご家庭もあるようです。ケープを使用するだけでも雰囲気が出ます。 ◎赤ちゃんの授乳のしやすさなどから、最近は正式な祝い着よりもベビードレスが増えてきているようです。 ※お宮参りの衣装を決める際も、日程を決める際も、赤ちゃんとお母さんの体調を優先してください。 |
| [和服・和装の場合] ◎白羽二重の着物(内着)に、紋の付いた祝い着を羽織る。男の子は、黒、紺、紫、白などの染め抜き五つ紋の羽二重地におめでたい図柄や男の子らしい図柄(兜、鷹など)ののし目模様の祝い着、女の子は、繻子や羽二重の赤、紅、ピンク、白などの地色に花、御所車などの模様の祝い着を着ます。 熨斗目模様は、袖と身ごろの部分の柄が横一直線につながったもので、七五三の5歳の男児の衣装としても知られています。 [洋服・洋装の場合] ◎ベビードレス、帽子、靴、祖母が赤ちゃんをだっこする時に赤ちゃんと一緒に包み込むケープ。 |
スポンサードリンク
| (2)お宮参り 赤ちゃんの両親の服装 | |
| ◎正式なお宮参りでは、母親は訪問着や色留袖などを着るのですが最近はスーツ、ワンピースなどを着るケースが多くなっています。 ※お宮参りの衣装を決める際も、日程を決める際も、赤ちゃんとお母さんの体調を優先してください。 |
|
| [男性] | [女性] |
| 男性の場合、和服でのお宮参りは非常に少なくなっています。
[洋服・洋装の場合] ◎ブラックスーツ、 (または ダークスーツなど) ※ダークスーツは正装とは言えないのですが、女性の方が正装でなければ、男性はダークスーツで格を合わせることもできます。 ブラックスーツの場合にはネクタイも慶事用の白黒ストライプ、白銀ストライプ、などを用いますが、ダークスーツの場合には、ネクタイはお祝いらしい色でば良いでしょう。 黒一色はNGです。 |
[和服・和装の場合] ◎訪問着、色留袖、 (または付下げのうち伝統的な絵柄のものなど) ※付下げは正装とは言えないのですが、絵柄によっては訪問着と同等の格のものがあります。そうした付下げを着ても良いでしょう。 [洋服・洋装の場合] ◎スーツ、ワンピースなど |
| (3)お宮参り 赤ちゃんの祖母の服装(参考:祖父の服装もご紹介します) | |
| ◎正式なお宮参りでは、祖母も黒留袖か色留袖を着るのが正式です。祖父も同行する場合には、祖母が正装のなら祖父も服装の格を合わせます。 | |
| [男性] | [女性] |
| 男性の場合、和服でのお宮参りは非常に少なくなっています。もし祖父が同行する場合には、祖父の服装の格は祖母に合わせます。
[洋服・洋装の場合] ◎ブラックスーツ、(または ダークスーツなど) ※ダークスーツは正装とは言えないのですが、女性の方が正装でなければ、男性はダークスーツで格を合わせることもできます。 ブラックスーツの場合にはネクタイも慶事用の白黒ストライプ、白銀ストライプ、などを用いますが、ダークスーツの場合には、ネクタイはお祝いらしい色でば良いでしょう。 黒一色はNGです。 |
[和服・和装の場合] ◎黒留袖、色留袖、訪問着 [洋服・洋装の場合] ◎スーツ、ワンピースなど |
スポンサードリンク

| 3-2.七五三の服装 |
|
七五三は、子供の健康を祝うとともにこれからの健やかな成長と幸せを祈る儀式です。もともとは11月15日に行なわれていましたが、最近では15日にこだわらず、その前後の土日に行なわれるようになりました。 男の子、女の子、それぞれについてお祝いする年齢は地域によって少し異なりますが、男の子は3歳と5歳(または5歳のみ)、女の子は3歳と7歳にお祝いをします。 |
| (1)七五三のお祝いの男の子、女の子の服装 | ||
| 三歳のお祝いは「髪置の儀」(=かみおきのぎ。髪を伸ばしはじめる儀式という意味)
、 五歳のお祝いは「袴着の儀」(=はかまぎのぎ。男児が初めて袴をつける儀式という意味)、 七歳のお祝いは「帯解の儀」(=おびときのぎ。女児が始めて帯を使って着物を着る儀式という意味)とされています。 ◎例えば「三歳の子供はまだ帯を結ばない」など、上記の儀式の慣習に合わせた服装があります。三歳、五歳、七歳という年齢によって衣装が異なります。 ◎七歳の女の子の着物は振袖を肩上げ、身上げをします。これは、大きめの着物を身体の大きさに合うように、肩のところで折り返して寸法を合わせたり、腰のところで折り上げて裾の長さが合うようにするものです。子供はすぐに成長するものですが、背が伸びても着られるようにという先人たちの知恵ですね。 |
| 男の子と女の子の七五三の服装 洋服の場合 | ||
| 男の子の服装 | 女の子の服装 | |
| [洋服・洋装] スーツ、タキシードなど (5歳のときは、入園式でも着られるものを選ぶと良いでしょう。) |
[洋服・洋装] ドレス、ワンピースなど (7歳のときは、入学式でも着られるものを選ぶと良いでしょう。) |
|
| 男の子と女の子の七五三の服装 和服の場合 | ||
| 年齢 | 男の子の服装 | 女の子の服装 |
| 3歳 | ||
| 男の子の服装 | 女の子の服装 | |
| [和服・和装] 羽二重熨斗目模様の紋付二枚重ねにへこ帯びと、袖のない羽織り。 |
[和服・和装] 晴れ着に帯を結ばず、羽織の代わりとして袖無しの朱色の「被布(ひふ)」を着用します。 他に草履、足袋、巾着など。 [髪型・髪飾り] 子供は髪が柔らかくて細いので、三歳児の髪飾りとしては、かんざしなどよりも、まとめ髪にして、和風のシュシュや小さなお花の髪飾りなどがおすすめです。 短い髪でもちょっとゴムなどでまとめて飾りをつけるだけでもぐっと可愛く仕上がります。 |
|
スポンサードリンク
| 男の子と女の子の七五三の服装 和服の場合 つづき | ||
| 年齢 | 男の子の服装 | 女の子の服装 |
| 5歳 | ||
| 男の子の服装 | 女の子の服装 | |
| [和服・和装] 黒の紋付に袴の羽織袴スタイルが基本。雪駄を履きます。兜、龍、鷹など勇壮な絵柄の羽織がある。 写真撮影時には、貸衣装とセットで、扇子や刀を着用することもある。 |
||
| 7歳 | ||
| 男の子の服装 | 女の子の服装 | |
| [和服・和装] 振袖(肩上げ、身上げ)、袋帯(結び帯が手軽)、草履、バッグ、足袋、帯締め、帯揚げなど。他に箱せこ、扇子なども。 [髪型・髪飾り] まとめ髪にしたり、つけ髪をつけたりアレンジ自在です。かんざしをはじめ、段飾り、櫛飾り、大降りのコサージュなど、大人と同じように飾ることができます。 |
||
| (2)七五三の両親の服装 | |
| ◎子供と一緒に両親がお参りする際の服装です。 もしおじいちゃんおばあちゃん(祖父母)も同行する場合には両親に準じます。 |
|
| 男性の服装 | 女性の服装 |
| [洋服・洋装] スーツにネクタイが最も一般的です。 |
[和服・和装] 留袖、訪問着 [洋服・洋装] スーツ、ワンピース。 |
| 3-3.成人式の服装 |
| 成人式には、記念写真を撮る人が増えています。大人になった報告を兼ねてぜひおじいちゃんおばあちゃん(祖父母)にも見せたいものです。 |
| (1)成人式の服装 | |
| ◎参列者は、一周忌(または初盆)の頃までの法事・法要に参列する際には略式礼服、喪服を着用します。
※法事・法要の服装の詳細は別ページでも説明しています>>> |
|
| 男性の服装 | 女性の服装 |
| [和服・和装] 羽織袴 ※レンタルの利用も多いようです。 [洋服・洋装] スーツにネクタイが最も一般的です。 ※成人式用にというよりも、社会人になってから使えるようにダークスーツを一着作っておくか、リクルートにも使えるスーツを作っておくと良いでしょう。 |
[和服・和装] 振袖 ※レンタルの振袖もあります。振袖は礼服の中でも「正装」として着用できます。購入した後も、結婚式などの席に着用することができるほか、パーティーや結納などにも着用できます。袖を短く仕立て直して訪問着にすることもあります。 [洋服・洋装] スーツ、ワンピース。 |
スポンサードリンク