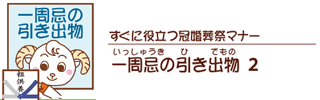
一周忌の引き出物とは、一周忌の法事・法要の際に参列者へのお礼の品として用意する品物をさします。ここでは一周忌の引き出物の金額相場や、引き出物として人気の品物(お菓子・引き菓子ほか)をはじめ、お寺・僧侶へのお礼について解説します。
なお、一周忌の引き出物ののしの表書き・のしの書き方をはじめ、遠方から香典やお供物を送って下さった方へのお礼状として送る一周忌の挨拶状は前のページをご覧下さい。
| ………このページの内容……… |
|---|
| ▼1. 一周忌の引き出物とは? 前のページ |
| ▼2. 一周忌の引き出物、のしの表書き、のしの書き方 前のページ |
| ▼3. 一周忌に香典、お供物などを送って下さった方へ(挨拶状) 前のページ |
| ▼4. 一周忌の引き出物 金額 相場 |
| ▼5. 一周忌の引き出物 人気の品物(お菓子、引き菓子) |
| ▼6. 一周忌 お寺・僧侶へのお礼 |
| [関連ページ] |
| ※関連ページ…一周忌法要のやり方、準備、マナー>>> |
| ※関連ページ…一周忌の案内状、一周忌法要のあいさつ>>> |
| ※関連ページ…一周忌を家族だけで行う場合のマナー>>> |
| ・三回忌の香典 金額相場は?>>> |
| ・七回忌の香典 金額相場は?>>> |
4.一周忌の引き出物 金額 相場
一周忌の引き出物の金額の相場は、香典として頂く金額の1/2〜1/3くらいが適当と言われています。2,000円〜5,000円程度が一般的です。
| 一周忌の引き出物金額相場 | ||
| ※下記は香典金額を考慮した引き出物の予算の一般的な例です。年齢やおつきあいの深さによっても変わってまいります。 一周忌の引き出物の相場=[頂く香典(左欄)の 半額〜1/3] |
||
| 故人との関係 | ||
| 一周忌の香典の相場 (★) | 一周忌の引き出物の相場 | |
| 1.故人と血縁関係がある場合 | ||
| 一周忌の香典の相場 (★) | 一周忌の引き出物の相場 | |
| 10,000円〜30,000円 | 3,000円〜10,000円 | |
| 夫婦で出席する場合 ※[会食なし] 20,000円〜50,000円 |
夫婦で出席する場合 ※[会食なし]5,000円〜20,000円 |
|
| 夫婦で出席する場合 ※[会食あり] 30,000円〜 |
夫婦で出席する場合 ※[会食あり] 引き出物の予算から食事分は割り引いて考えても良い 5,000円〜10,000円 |
|
| 会食がある場合には、引き出物の予算から食事分は割り引いて考えても良いでしょう。 また、故人の親族にあたる相手が、法要の儀式を執り行う費用の一部を負担する意味も込めて香典を包んでいる可能性もあるので、キッチリと半返し〜3分の1返しにこだわらずとも、それよりも控えめな金額で構いません。 |
||
| 2.故人と血縁関係がない知人・友人 | ||
| 一周忌の香典の相場 (★) | 一周忌の引き出物の相場 | |
| 5,000円〜10,000円 | 2,000円〜5,000円 | |
| (★)一周忌の香典の相場についての詳細はこちらを参照して下さい。 | ||
スポンサードリンク
一周忌法要の引き出物 |
| ●一周忌の法要のあと、お持ち帰り頂くものとして検討したいものは以下の通りです。 1)引き出物
2)会食がなければ持ち帰り用のお弁当 3)持ち帰り用のお酒 (必須ではありません。会食がなければお弁当とお酒を付けるケースが多いものですが、会食ありでもお酒を引き出物の一つとして付けることがあります) 4)引き菓子(必須ではありません) 5)(故人の親族であれば)祭壇のお供物を親族で取り分けたもの この中で引き出物として人気の品物と引き菓子について解説します。 |
| 引出物にはどんなものを? |
| ・引き出物に多く使われるものとしては、石鹸、洗剤などの実用品や、お茶、お菓子、海苔などの食品で、金額のめやすとしては、2,000円〜5,000円程度の品物が一般的です 。 実用品や食品などの消えもの(消えもの=消費されて消えてなくなるもの)が多く、インテリアや食器などの残るものはあまり向きません。 引き出物としてお菓子を用意する場合には、別途引き菓子を用意するケースが少なくなります。 ※法要の後の会食あり・なしに関わらず引き出物と一緒にお持ち帰り頂くためのお酒の小壜をつける地方もあります。 |
| 人気の引き菓子は? |
| ・引き菓子の条件は「持ち帰る」ことを想定し、日持ちするもの、かさばらないものです。引き出物と一緒にお持ち帰りいただきます。 ・和菓子でも洋菓子でもOKで、1000円〜3,000円程度のものが良く用いられます。 [人気の引き菓子] ・クッキー、焼き菓子、あられ、せんべいなどの詰め合わせ、家族で分けられる小分け包装のものが喜ばれます。 [引き出物として菓子を用いる場合] 夏場の法要であれば、ゼリーやプリン、水ようかん(いずれも数日は日持ちするものを)などの季節感があるものを用いることもあります。 また、夏場は敬遠されがちなチョコレート系の菓子も冬場であれば用いることもあります。 引き出物として菓子を用いる場合には、別途引き菓子をつける必要はありません。 |
| つづく |
スポンサードリンク
| 引き出物に印をつける | |
| ・もし、他の人とは異なる引き出物を用意する場合には、お持ち帰り頂く際にすぐにわかるように印をつけます。 ●夫婦で法要に出席する人の引き出物 ●金額が異なる引き出物 ●僧侶にお渡しする引き出物 ●特にお世話になった人の引き出物など |
6. 一周忌 お寺・僧侶へのお礼
お寺には一周忌の法要を行うことを連絡し、日程と場所を伝えてご住職・僧侶の都合を確認します。もし、法要のあとで会食を行う場合には、会食にも出ていただけるかを尋ねます。
例えば「法要のあと、お食事をご用意したいのですが、宜しければ和尚様もご一緒していただけませんでしょうか」などと和尚様のご都合をお聞きしてください
(※会食への出欠を尋ねるこの質問は、法事の後でお布施や謝礼をお渡しする際に役に立ちます)
※ご住職(僧侶)に対して呼び掛ける時は「和尚様(おしょうさま)」「ご導師様」などとお呼びするのが無難です。
「ご住職」とお呼びすることができるのは、そのお寺で代表者となる方だけなので、僧侶が一人だけのお寺、または代表者であることがわかっている場合ならOKです。
この他にはご院家様(ごいんげさま)」とお呼びすることもありますが宗派によるようです。また、日蓮宗では「お上人様(おしょうにんさま)」、禅宗の一派では「方丈様」などがあります。心配な場合は年配の人などに確認をしておきましょう。
当日は以下のようにお礼を用意しておきます。
| 一周忌 お寺・僧侶へのお礼 |
| ◆施主が準備すること |
| 料理の手配 または レストランなどの予約 | |
| ・一周忌法要の後で会食(お齋)を行う場合には、必要に応じて仕出し料理やレストランなどの予約をします。 ・ 献立に、おめでたい鯛や伊勢海老などのご祝儀料理が入ることの無いように「一周忌の法要のあとの、お食事」と伝えた上で、日程と人数、予算を告げて予約をします。自宅から移動する場合に必要があれば送迎用の車なども手配します。 ・会食は行わなくても失礼にはあたりません。その場合は法事のあと引き出物と一緒にお酒と折詰弁当などをお持ち帰り頂きます。 |
|
| 引き出物 | |
| ・法要のあとで僧侶にお渡しする引き出物の手配をします。 もし僧侶が会食に出席せずに帰られる場合には、事前に僧侶に渡す引き出物は別にしておきます。 ・お寺へのお礼としてお渡しするのはお布施なので、お寺への引き出物についてはこだわって特別なものを用意する必要はありません。参列者の皆さんと同じもので構いません。 |
|
| お布施ほか | |
| ・一周忌法要のあとで僧侶にお渡しするお礼(お金)をお布施と言います。法要を寺でなく自宅で行う場合には、「お布施」の他に「お車代」を用意します。 もし、法要のあとの会食に僧侶が出席しない場合にはこれらとは別に「御膳料」という形で現金を包みます。 詳細は次の項で説明します。 ・お布施をお渡しする時には、直接手渡しするのではなく、お盆に載せてお渡しするのが正式な作法なので、小さなお盆も用意しておきましょう。 |
|
スポンサードリンク
一周忌法要の際に僧侶に渡す「お布施」「お礼」について(つづき) |
||
| 施主が準備すること(つづき) | ||
| ◆お布施の準備 | ||
| 僧侶に法要のお礼を渡す際の、袋の書き方は? | ||
・ 表書きは「御布施」「お布施」「御経料」などです。 ・下段は、この見本画像のように「◯◯家」と施主の姓を書くか、または施主の氏名をフルネームで書きます。 ・薄墨ではなく黒い墨で(真っ黒の墨で)書きます。 ・本来は半紙の中包みに入れて、奉書紙で包むのが最も正式な形です。のし袋は用いません。この場合の封筒は、二重になっているものは使わないようにします。(「不幸ごとが重なる」といわれます。二重封筒は避けた方が良いでしょう。) 郵便番号の欄の無いものを選んでください。 |
||
| お布施の金額はどのくらいを包む?(お布施の金額の相場は) | ||
| ・お布施または御経料の金額相場は30,000円程度〜です。 一般的なお布施の金額の目安ですが、心配な場合には法要の予約をする際にお寺に料金を確認してください。 |
| ◆お車代の準備 |
| 自宅や、その他の会場で法要を行う場合の交通費は? |
・ 表書きは「お車代」が一般的です。 ・下段は、なし。 ・薄墨ではなく黒い墨で(真っ黒の墨で)書きます。 |
| ・袋は、熨斗袋ではなく、白い封筒を使います。この場合の封筒は、二重になっているものは使わないようにします。郵便番号の欄の無いものを選んでください。 |
| お車代の金額はどのくらいを包む?(交通費の金額の相場は) |
| ・車やバイクなど、僧侶自身の運転でおこしいただいた場合、5,000円〜10,000円くらいをお車代として包みます。送迎タクシーを施主が手配し、タクシー会社へ実費を支払うこともあります。 |
| つづく |
スポンサードリンク
| 一周忌法要の際に僧侶に渡す 「お布施」「お礼」について(つづき) |
| ◆お膳料の準備 |
| 僧侶が、会食を辞退された場合には? |
・ 表書きは「御膳料」が一般的です。 ・下段は、なし。 ・薄墨ではなく濃い墨で(真っ黒の墨で)書きます。 |
| ・袋は、熨斗袋ではなく、白い封筒を使います。この場合の封筒は、二重になっているものは使わないようにします。郵便番号の欄の無いものを選んでください。 ※会食そのものを実施しない場合には、折り詰めの料理、お酒の小壜などをお持ち帰り頂きます。 |
| 御膳料の金額はどのくらいを包む?(御膳料の金額の相場は) |
| ・地方によって、また、法要の会場によっても異なりますが御膳料としては5,000円〜20,000円くらいです。 |
| 僧侶に「お布施」を渡す時 お布施の渡し方 |
| 僧侶にお礼・お布施をお渡しするタイミングは? 会食がない場合には、施主は法要が終わったらお礼の挨拶をして僧侶にお布施(およびお車代、お膳料、引き出物など)を手渡します。 もし会食がある場合はお誘いし、会食後にお帰りになる際にお布施(およびお車代、引き出物など)をお渡しします。 お布施を渡す時の施主の挨拶の言葉や、切手盆に乗せて渡すなどの渡し方の詳細はこちらで解説します>>> |
スポンサードリンク