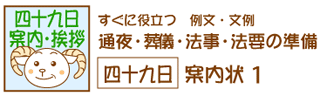
| ………このページの内容(カッコ)は別ページ……… |
|---|
| ▼1. 四十九日とは? 法事・法要とは? |
| ▼2. 四十九日法要の案内(法事の案内状の書き方・例文・文例) |
| ▼3. 四十九日法要の案内状(レイアウト例) |
| ▼4. 四十九日法要の案内状 次のページへ (往復はがきを使う場合)(宛名の書き方) |
| ▼5. 四十九日法要の準備(引き出物、お供え。お返し) 次のページへ |
| ▼6. 四十九日の法要の挨拶(施主の挨拶の文例・例文) 次のページへ |
| ▼7. 四十九日の頃に送る忌明けの挨拶状(お礼状) 次のページへ |
| 関連ページ |
| ※ 四十九日のマナー、お布施や香典の書き方、金額の相場>>> |
| ※ 四十九日 香典袋 は別ページへ>>> |
| ※ 四十九日 お供え は別ページへ>>> |
| ※ 四十九日のお供え のし は別ページへ>>> |
| ※ 四十九日のお供え花 種類・マナーは別ページへ>>> |
| ※ 四十九日のお供え のお返し 別ページへ>>> |
| ※ 四十九日 挨拶(喪主、参列者、献杯)は別ページへ>>> |
| ※ 四十九日 挨拶状(忌明けの挨拶状)は別ページへ>>> |
| ※ 四十九日 男性の服装 別ページへ>>> |
| ※ 四十九日 女性の服装 別ページへ>>> |
1.四十九日とは? 法事・法要とは?
仏教において故人を供養する儀式を法要と言います。
亡くなってから七日目に行う「初七日」から、四十九日めに行う「四十九日」までの法要を追善法要と言い、四十九日目で忌明けとなります。この間、一般的には初七日以外の法要は遺族だけで供養が行なわれますが、四十九日の法要だけは忌明けの日として親族・友人・知人たちも参列し、僧侶による読経のあと、焼香や会食が行なわれます。
●追善法要と年忌法要
[追善法要]
四十九日までの間、七日ごとに閻魔大王(えんまだいおう)による裁きが行なわれ、最終的に極楽浄土にいけるかどうかの判決が下されるのが四十九日目だと言われています。閻魔様に少しでも良い判決をしてもらうために故人が生前に行なった善行に(ぜんこう=よいおこない)、遺族が祈ることによって善を足す、善を追加するという意味で「追善法要(ついぜんほうよう)」と呼ばれます。
[年忌法要]
命日から一年目、三年目、七年目など、節目となる年ごとに行われる法要を年忌法要と言い、一周忌とは亡くなってから満一年目の同月同日のことを言います。また、命日と同じ月の同じ日が毎年一年に一度やってきます。この日のことを祥月命日と言います。
なお、厳密には法事という言葉は仏教の行事全般をさしますが、法要は追善法要および年忌法要のことをさします。
●四十九日は非常に重要
四十九日は忌明けということで、故人を供養するにあたってひとつの節目となります。そのため、「納骨・納骨式」は四十九日に合わせて行なわれることが最も多いほか、仏壇が無いお宅ではこの日までに新規に仏壇を準備し「開眼供養」は四十九日の法要までに行なわれます。
[納骨・納骨式]
=遺骨をお墓に埋葬する儀式。納骨は四十九日に行なわれることが多いようです。四十九日の日に行なわない場合でも遅くとも三回忌の頃までに済ませます。
[開眼供養]
=仏壇開きとも言われ、魂を入れた本位牌を仏壇に安置する儀式です。
[香典返し]
=通夜・葬儀に香典を頂いた相手に、お礼状を添えて香典返しを送ります。一般的に四十九日の忌明けにタイミングを合わせて手配をします。
※参考ページ「香典返し」>>>
この項では主な法事の名称と日数の数え方一覧表を掲載します。>>>
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| 四十九日法要の案内(案内状の書き方) | |
| 項目 | 内容とポイント |
| ◆四十九日の案内状の書き方(必要なポイント) | |
| 誰の何日目の法要かを伝える | |
| ・故人の氏名、施主の氏名、四十九日の法要を行うという目的を知らせます。 | |
| 日程と場所を知らせる | |
| ・四十九日法要をいつ、どこで行うのかを知らせます。 また、法要のあとで会食がある場合は、その旨をお知らせします。 ・本来は亡くなってから49日目に行うものですが、実際には遺族や参列者の都合を考えて、その直前の土曜または日曜日に四十九日法要を行う場合も増えています。 ・四十九日法要では、読経、会食(お齋と言います)の他にも、以下の1〜5のような行事を行う場合があります。この中で何を行うのかを案内状に記載します。 下記の1〜5のうち通常四十九日の法要に合わせて行われるのは1法要,2会食,5納骨 です。菩提寺で四十九日の法要を営む場合には1〜5の全てを行なうことができますが、自宅で四十九日の法要を行なう場合には(墓地が遠方という事情があれば)、3の墓参りと5の納骨は別 途遺族のみで催すことにし、法要と会食のみ、または法要のみを友人、知人を招いて行なうということもあります。 ▼1,法要(僧侶による読経。遺族、参列者による焼香)。 ▼2,会食(お齋=おとき、と読みます)。 ▼3,お墓参り ▼4,卒塔婆供養 ▼5,納骨(納骨は四十九日の頃に行うの場合が最も多いのですが、四十九日に合わせて行われることもあります。) |
|
| 出欠をたずねる | |
| ・会場の準備、引き出物や料理の手配のため、法要への出欠を確認します。返信用のハガキを同封するか、往復はがきの返信欄を使います。 | |
| ◆法事の案内状の作成において注意すること | |
| 文中に句読点は用いない | |
| ・法事・法要をはじめお悔やみごとの案内状や、遺族が出すお礼状には句読点の「、」「。」は用いません。句読点がなぜ使われないかについては大別して下記の3つの説があります。 ▼1,本来、書状は毛筆で書かれていた。毛筆の書状には近年まで「、」「。」が使われなかったという慣習が残ったもの。 ▼2,法事や葬儀が滞り無く流れ、つつがなく終わるように、途中で区切るための「、」「。」は用いない。 ▼3,もともと句読点は読む人が読みやすいようにつけられたものであり、句読点がなくても読みとる力を持っている相手に対して句読点を付けるのは失礼にあたるということから、相手への敬意を表わすため。 |
|
| 封筒に入れる場合、二重封筒は用いない | |
| ・法事を知らせる案内文を書いた書状は、ふつうは封筒に入れて出すのがマナーです。 この時に使う封筒は、二重封筒は用いません。 二重封筒は不幸が重なると言われ、使わないのがマナーです。白い無地の封筒が使われます。 ・近年は略式として封筒を用いずに往復ハガキを使うケースもあるようです。 |
|
スポンサードリンク
| 四十九日法要の案内状(例文・文例) | |
| 例1)自宅で四十九日法要を行う場合 | |
| ◆テキストデータを用意しました。ページ作成の都合上、横書きで紹介しております。 ただし 例文の2行目の「左記のとおり」という箇所は縦書きに書き直すことを想定した文章です。 印刷の際のレイアウト例については、このページの別項でイラスト画像を紹介していますので、ご参照下さい。 ※)文中 句読点「、」「。」は用いません。 |
|
謹啓 ○○の侯
皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます
このたび亡祖父 治朗の四十九日にあたり左記のとおりささやかな法要を営みたいと存じます
つきましてはご多忙中まことに恐れいりますが ご参会賜りますようご案内申し上げます 敬具
令和○○年○月
住所 ○○市○○町 ○−○−○
電話 ○○○−○○○−○○○○ 鈴木 太郎 ※お手数ではございますが○月○日までに返信にてご都合をお知らせ下さい。
|
| 四十九日法要の案内状(例文・文例)2 | |
| 例2)お寺やホテルなどで四十九日法要を行う場合 | |
| ◆テキストデータを用意しました。ページ作成の都合上、横書きで紹介しております。 ただし 例文の2行目の「左記のとおり」という箇所は縦書きに書き直すことを想定した文章です。 印刷の際のレイアウト例については、このページの別項でイラスト画像を紹介していますので、ご参照下さい。 ※)施主と故人の姓が異なる場合には、故人の名前はフルネームを書きます。 ※)文中 句読点「、」「。」は用いません。 |
|
謹啓 ○○の侯
皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます
このたび左記日程にて亡父一夫の四十九日法要を営むことになりました
つきましてはご多忙中まことに恐縮ではございますが ご参会賜りますようご案内申し上げます 敬具
令和○○年○月
住所 ○○市○○町 ○−○−○
電話 ○○○−○○○−○○○○ 鈴木 太郎 ※お手数ではございますが○月○日までに返信にてご都合をお知らせ下さい。
|
|
| ※)また、会社関係で営む法事の場合は 「拝啓 ○○の候 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます このたび左記日程にて故 弊社前相談役 ○○○○の四十九日法要を営むことに相成りました」 などとなります。大規模な法要の場合には、案内状に添えて地図や駐車場所在地なども同封する気配りも忘れないようにしましょう。 |
スポンサードリンク
| 四十九日法要の案内状(例文・文例)3 | |
| 例3)会社で法要を行う場合 | |
| ◆テキストデータを用意しました。ページ作成の都合上、横書きで紹介しております。 ただし 例文の2行目の「左記のとおり」という箇所は縦書きに書き直すことを想定した文章です。 印刷の際のレイアウト例については、このページの別項でイラスト画像を紹介していますので、ご参照下さい。 ※)文中 句読点「、」「。」は用いません。 |
|
拝啓 ○○の候 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます
このたび左記日程にて故 弊社前相談役 鈴木太助の四十九日法要を営むことに相成りました
つきましてはご多忙中まことに恐縮ではございますが ご参会賜りますようご案内申し上げます 敬具
令和○○年○月
住所 ○○市○○町 ○−○−○
電話 ○○○−○○○−○○○○ 株式会社 ベストマナー 代表取締役 鈴木太郎 ※お手数ではございますが○月○日までに返信にてご都合をお知らせ下さい。
|
スポンサードリンク
 誰の何回忌の法要なのかを知らせます。
誰の何回忌の法要なのかを知らせます。上の文例では「亡父太助の四十九日の法要」という箇所です。もし、施主と故人の姓が異なる場合(名字が違う場合)にはフルネームを書きます。四十九日のことを満中陰の法要と書いても良いでしょう。 文例: 「ささやかながら亡義父鈴木一夫の四十九日の法要を営みたいと存じます」など。 |
|
 日程を知らせます。
日程を知らせます。法事を行う日付、曜日、開始時刻を知らせます。 |
|
 場所を知らせます。
場所を知らせます。上の画像の例では、○○寺となっています。 住所と電話番号は必ず記載します(当日の連絡先を知らせるために、電話番号が必要です)。 自宅の場合は自宅と書きます。ホテルなどで行う場合、部屋の名称がわかれば「西の間」などと具体的に記載します。 |
|
 法要のあとで会食(お齋)がある場合は出席者に知らせます
法要のあとで会食(お齋)がある場合は出席者に知らせます会食の有無により、出席者におよその所要時間が伝わります。出席者も何時間くらいかかるかがわかれば時間の都合のつけかたが変わります。会食の予定がある場合には必ず知らせます。 |
|
 施主の住所、氏名、連絡先を書きます
施主の住所、氏名、連絡先を書きます住所と電話番号は必ず記載します(当日の連絡先を知らせるために、電話番号が必要です)。 |
|
 返信の依頼と、返信期限を書きます
返信の依頼と、返信期限を書きます往復はがきの場合には 「お手数ですが中央の折り目のところでお切り取りの上、ご出欠を○月○日までに返信にてお知らせ下さい。」 「お手数ですが中央にて切り取り、返信のみ○月○日までにポストにご投函下さい」など |
| ………以下は別ページ……… |
|---|
| ▼4. 四十九日法要の案内状 次のページへ (往復はがきを使う場合)(宛名の書き方) |
| ▼5. 四十九日法要の準備(引き出物、お供え。お返し) 次のページへ |
| ▼6. 四十九日の法要の挨拶(施主の挨拶の文例・例文) 次のページへ |
| ▼7. 四十九日の頃に送る忌明けの挨拶状(お礼状) 次のページへ |
| 関連ページ |
| ※ 四十九日のマナー、お布施や香典の書き方、金額の相場>>> |
| ※ 四十九日 香典袋 は別ページへ>>> |
| ※ 四十九日 お供え は別ページへ>>> |
| ※ 四十九日のお供え花 種類・マナーは別ページへ>>> |
| ※ 四十九日のお供え のお返し 別ページへ>>> |
| ※ 四十九日 挨拶(喪主、参列者、献杯)は別ページへ>>> |
| ※ 四十九日 挨拶状(忌明けの挨拶状)は別ページへ>>> |
| ※ 四十九日 男性の服装 別ページへ>>> |
| ※ 四十九日 女性の服装 別ページへ>>> |