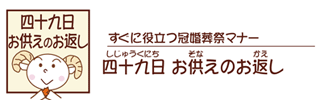
| ………このページの内容……… |
|---|
| 1. 四十九日 お供えのお返しとは? |
| 2. 四十九日 お供えのお返し 用意するものは? 品物、のしの表書き、墨の色、金額相場は |
| [関連ページ] |
| ※別ページ…四十九日法要(法事法要の流れ、お布施、香典)>>> |
| ※別ページ…四十九日 お供え>>> |
| ※ 四十九日のお供え のし は別ページへ>>> |
| ※ 四十九日のお供え花 種類・マナーは別ページへ>>> |
| ※別ページ…四十九日の香典袋(書き方、金額相場)>>> |
| ※ 四十九日 挨拶(喪主、参列者、献杯)は別ページへ>>> |
| ※ 四十九日 挨拶状(忌明けの挨拶状)は別ページへ>>> |
| ※関連ページ…四十九日 男性の服装 別ページへ>>> |
| ※関連ページ…四十九日 女性の服装 別ページへ>>> |
1.四十九日のお供えとは?
法事・法要の際には、祭壇(または仏壇)にお供物をお供えします。
主なものには以下のようなものがあり、五供(ごくう)と言われます。
線香
花・供花
ろうそく・灯明
飮食(おんじき)・仏飯
お水 など
施主や遺族はこれらを用意するほか、参列者は線香の代わりにお香典を持参したり、飮食の一つとして果物や菓子をお供えしたり、供花をお供えしたりします。
2. 四十九日 お供えのお返し 用意するものは?
四十九日法要で頂く香典、供花、お供物は四十九日のお供えにあたります。施主はこれらを頂いたお返し・返礼品を以下のように用意します。
品物、のしの表書き、墨の色、金額相場について解説します。
| 四十九日 お供えのお返し |
|
四十九日法要でのお返しを、法事の引出物として用意します。 法要のあと会食があるなしにかかわらず、お供え(香典、供花、お供物)のお返しとして施主が用意するのは引出物(返礼品)です。 Q,会食と香典の関係は? ・四十九日には、案内を受けた人だけが出席します。もし会食がある場合には、出席者は会食分を見越した香典を包みますし、施主は忙しい中をわざわざ集まって頂いたお礼を込めて、それ以上のおもてなしをします。以下の引出物は、会食によるおもてなしとは別のものです。 ・四十九日法要のあと会食は行わなくても失礼にはあたりません。会食が無い場合は法事のあと引き出物と一緒にお酒と折詰弁当などをお持ち帰り頂きます。 |
「志」「粗供養」など。 (ちなみに、通夜葬儀の香典返しの表書きは「志」が一般的。関西では「満中陰志」と書く地域もあります) ・墨の色は? 一般的には薄墨ではなく濃墨を使います。 ・返礼品の金額相場は? 頂く香典の1/2〜1/3をめやすにします。金額のめやすとしては、2,000円〜5,000円程度の品物が一般的です。 |
スポンサードリンク
| 四十九日 お供えのお返し(つづき) |
| 引出物として用意するのは「消えもの」 不祝儀の引出物の定番は、石鹸や洗剤などの実用品、海苔、お茶、お菓子(日持ちするもの)です。 ほとんどの参列者に同等のものをお持ち帰り頂いた上で、香典の金額が大きい方にはカタログギフトなどでカバーすることもあります。 地方によっても異なりますので、葬儀社や年配の人に相談してください。 法要に出席できず香典やお供物、供花だけを頂いた相手にも、お礼状を添えて返礼品を送る形でお返しをします。品物を送るか、カタログギフトを送ることもあります。 |