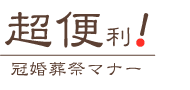不祝儀袋とは、通夜や葬儀葬式や法事などのお悔やみ・弔事の際に現金を包む水引きのついた袋で、お悔やみ用ののし袋、香典袋などとも呼ばれます。(不祝儀とは文字通り「祝儀でないこと」つまり通夜・葬儀葬式や法事法要などをさします。この時に使われる袋が不祝儀袋となります) 不祝儀袋には水引が印刷された簡易な袋から、袋が二重になった正式な不祝儀袋までありますが、中に包む金額に袋のグレードを合わせるのがマナーです。 このページでは通夜・葬式葬儀・法事の不祝儀袋の表書きの書き方、中袋の金額の書き方、お金の入方や向きなどを解説します。 |
1.不祝儀袋とは・不祝儀袋マナー
通夜や葬式葬儀または法事法要などの際に、お悔やみの気持ちを表わすお悔やみ金を包む袋を不祝儀袋と言います
(不祝儀袋の読み方=ぶしゅうぎぶくろ)。
不祝儀袋は、一般的には「お悔やみ用のし袋」「お悔やみのし袋」あるいはもう少し具体的に「香典袋」などと呼ばれます。
| (1)不祝儀袋の種類とマナー | ||
| 下の見本画像をご覧下さい。不祝儀袋には紐が結ばれており、これを水引きと言います。 また、慶事の際に使う祝儀袋には、紙を折り畳んで作った飾りがついていますが、この部分が本来は「のし」と呼ばれている部分です。 現代では、のしがついた袋ということでのし袋と呼ばれることが多くなっています。ちなみに、慶事用の袋(祝儀袋)にはのしが付いていますが、弔事の袋(不祝儀袋)にはのしはつきません。弔亊用の熨斗紙も同様です。 また、お祝い用の熨斗であっても生物(なまもの)を包む場合にはのしの部分はついていないものを使います。 お悔やみ用に用いる袋(不祝儀袋)は、下記のような袋です。 |
不祝儀袋 |
祝儀袋 |
|
 |
 |
 |
| 水引きは結び切り | 水引きは蝶結び | 水引きは結び切り |
| 結び切りは、水引きを固く結んであり、解くのが難しいため、葬儀葬式などのように人生に一度きりにしたいお悔やみごとに使います。 | 蝶結びは、簡単に水引きを結んだりほどいたりすることができるため、出産祝いや子供の成長のお祝い、あるいは長寿祝いなど、人生に繰り返し何度もあると嬉しいお祝いに使います。 | 結び切りは、水引きを固く結んであり、解くのが難しいため、結婚祝いのように人生に一度きりにしたいお祝いに使います。 |
スポンサードリンク
| (2)不祝儀袋の水引き | |
| お悔やみ事(「弔事」=ちょうじ)の時に使う不祝儀袋では、使う水引きの本数と色が決められています。 | |
| 1.水引きの色・水引の色 | |
| お悔やみ事の水引の色なら、白×黒(黒白)、白×銀、銀×銀(双銀)、白×白まれに白×黄(黄白=関西の一部地域のみ)など。 | |
| 2.水引きの本数 | |
| お悔やみ事なら2本、4本、6本など偶数。 但し結婚のお悔やみの不祝儀袋は5本×2束で10本の使用が許される。 |
|
| 3.水引きの位置 | |
| 濃い色が右側になるようにします。 | |
| (3)正式包み | |||||
ここでは水引きを外せるタイプ について説明します。 下記はうしろから見た図です。 市販されているのし袋は略式の封筒タイプ(袋タイプ)のものが一般的ですが、沢山のお金を包む場合などに使う正式な包み方があります 正式包みと呼ばれる包み方ですが、裏から見た場合に特徴がありますので、解説します。 覚え方のコツをご紹介します。 下記のイラストをご参照下さい。 |
|||||
| 正式包みの覚え方のコツをイラストにしてみました! 水引きをはずした時の後ろから見た図です。 |
弔事(うしろから見た図) |
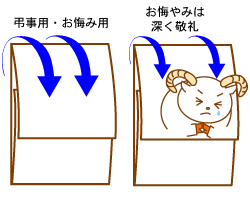 [お悔やみ事のときは上から下へ] |
慶事(うしろから見た図) |
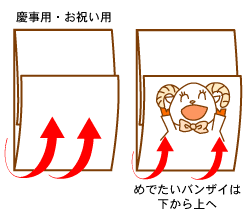 [お祝い事のときは下から上へ] |
スポンサードリンク
2.不祝儀袋の用途
[不祝儀袋の選び方]
・香典の金額に合わせた袋を選ぶ
不祝儀袋を選ぶ時には、中に入れる金額にふさわしい袋を選ぶようにします。例えば香典を数千円しか入れないのに、袋ばかりが立派では受け取り手も違和感があります。逆に高額の香典を包む時には、袋もそれなりに立派なものを選ぶようにします。
不祝儀袋の選び方のコツとしては、水引が印刷されているタイプは香典の金額が少ない時に使い、水引きが立派なものや使われている和紙が高級なものは、香典の金額が多い時に使います。水引きの色が銀色のものも、どちらかといえば高額の香典を包む時に使います。
・宗教宗派にふさわしい袋を選ぶ
蓮の花や蓮の葉がついた袋は仏教でしか使えないので注意して下さい。
[不祝儀袋の用途と表書き]
不祝儀袋の主な用途を紹介します。
| (1).不祝儀袋の用途 | ||
人生に一度きりで良いことに使います。 結び目のところがもう少し豪華な 「あわじ結び」という結び切りもあります (右はあわじ結び・あわび結びとも言う)。 これも結び切りの一種とされています。 |
| No. | 用途 | 解説 |
| 1 | 香典 | 通夜、葬式葬儀、法事法要などの悲しいこと、お悔やみは一度だけで良いもの。 |
| 2 | 御供物料 | |
| 3 | 御供花料 | |
| 4 | 葬儀の引出物 | |
| 5 | 香典返し | |
| 6 | 法事法要の引出物 | |
| 7 | お寺神社などへのお礼 | 葬儀などの謝礼を払うときに使うのは不祝儀袋ですが、不祝儀袋を使わずに白封筒や奉書紙を使う方(中包みに入れて上包みをかけ、水引きをつけない)が丁寧です。 |
| (2). 不祝儀袋の表書き | ||
| No. | 用途 | 表書きと解説 |
| 1 | 香典 | |
| 通夜・葬儀 | |
・仏教の場合の熨斗の表書きは「御霊前」「御香料」などです。中でも最も一般的なのは「御霊前」で、この表書きは通夜・葬儀だけでなく四十九日(忌明け)より前の法要でも用いられます。 但し「御霊前」は浄土真宗以外で用います。 [墨] ・薄墨を用います。薄墨は悲しみの涙で文字が滲んでいるという気持ちを表わすとされています。 |
|
| ※キリスト教、神道の場合の書き方、連名の場合(夫婦連名、数人で連名)、会社名義の場合の書き方など 表書きの詳細は香典袋の表書きの書き方へ>>> | |
| 四十九日以降の法事法要 | |
・仏教の場合の熨斗の表書きは「御仏前」などです。 [墨] ・濃墨を用います。 |
|
| ※四十九日の香典袋、夫婦連名の場合の書き方などは「四十九日の香典袋へ}>>> | |
| 2へつづく | |
スポンサードリンク
| 2. 御供物料 | |
| ・「御供物料」「御供」という表書きは宗教を問わず使えます。 | |
| 3. 御供花料 | |
| ・「御供花料」「御花料」という表書きは宗教を問わず使えます。 | |
| 4. 葬儀の引出物 | |
| ・地方によって異なります。 単純に会葬者全員に渡す品物には「御会葬御礼」。 その他に香典返しを当日渡す場合には下記を添えます。 |
|
| 5. 香典返し | |
| ・地方によって異なります。 本来、香典返しは49日の忌明けの頃にお送りするものでしたが、最近では葬儀当日にお渡しする「即日返し」も多くなってきています。 神式なら三十日祭または五十日祭の後の頃に。 キリスト教は一ケ月後に昇天祭(プロテスタント)、追悼ミサ(カトリック)の頃に送ります。これらも即日返しが増えています。 【表書き】 ・宗教を問わず使える表書きは「志」 宗教別では仏教なら「志」「満中陰志」、神式なら「志」「偲び草」「茶の子」、キリスト教式なら「志」が無難ですが、他に「昇天記念」など。 |
|
| 6. 法事法要の引出物 | |
| 【表書き】 ・仏教なら「粗供養」など。 |
|
| 7. お寺神社などへのお礼 | |
葬儀などの謝礼を払うときに使うのは不祝儀袋ですが、御礼に不祝儀袋を使うのに抵抗がある方もいらっしゃいます。不祝儀袋を使わずに白封筒を使います。最も丁寧な形は奉書紙を使う方法(中包みに入れて上包みをかけ、水引きをつけない)です。 |
|
| 8. その他の方への御礼 | |
| ・火葬場の係員や、手伝って下さった方などに謝礼を包むことがあります。表書きは「御礼」が一般的です。「寸志」は目下の相手にしか使えないので注意して下さい。白封筒が無難ですが不祝儀袋でも可。 | |
スポンサードリンク
3.中袋の書き方・金額の書き方
香典袋には、中袋または中包みと呼ばれる袋が入っています。
中袋(または中包み)には、中に入れたお金の金額を書き、会葬者の住所氏名などを書きます。
市販されているものの中には、「金額を書く欄」「住所氏名そ書く欄」が決められているものもあるようです。
不祝儀袋の中袋(中包みとも言います)などに書く金額の書き方について解説します。
| 香典の中袋・中包みの書き方 | |
| 項目 | 説明 |
| 筆記用具 | ||||||||||||||||||||||||
| ・筆を使うのが正式な作法ですが、筆ペンでも良いでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||
| 中に入れる金額 | ||||||||||||||||||||||||
| ・死や苦を連想させる数字として(四、九)がつく金額は避けるのが一般的です。少額の場合は連名で香典を出すなどして、 3千円、5千円、1万円、2万円、3万円、5万円、10万円、20万円、30万円など、キリの良い金額にします。 ・香典の金額の相場については、別ページ「香典の金額の相場とめやす」にて |
||||||||||||||||||||||||
| 香典の金額の書き方 | ||||||||||||||||||||||||
「一」「二」などの文字は後で線を書き加えるだけで簡単に数字の改ざんができてしまうため、数字の改ざんができないようにする…という考え方からきています。 (例:金一万円→金壱萬円など。) なお、最近では金額を書く欄が横書き用になっているものも市販されており、五千円、三万円などと横書きすることなく、アラビア数字で書く場合もあるようです (例:金5,000円、金30,000円など)。 具体的な書き方の見本は下記の画像を参照して下さい。 |
| 中袋の書き方 中包みの書き方 | ||
| ・香典の中袋の書き方です。下記のサンプル画像をご覧ください。 |
||
| 表面に金額を書く場合は、住所氏名は裏に | 裏面・うら面に金額も住所氏名も書く場合 | |
| 裏(おもて) | 裏(うら) | 裏(うら) |
 |
 |
 |
| ・金額については、中袋(中包み)の表面に書くという説と、裏面に書くという説があります。 ・市販の熨斗袋の中には、金額を記入する欄が決まっているものがあります。 ・通夜葬儀葬式など会葬者が多い場合には、香典袋から中袋を出して別々にした場合のために、中袋にも住所氏名を書くと丁寧です。ちなみに結婚式の場合には招待されているため中包みには住所は書きません。 ※住所氏名は中袋の裏面に書きます。 |
||
|
・香典の金額の相場については、別ページ「香典の金額の相場とめやす」にて ・中袋なし・中袋がない時は、別ページ「不祝儀袋の中袋・中袋がない時」にて |
||
スポンサードリンク
4. お金の入れ方と向き
不祝儀袋に入れるお札の入れ方と向きについて説明します。
| (1)香典に入れるお金・お札 |
| 通夜や葬儀などの際に包む香典は新札を用いるのはマナー違反です。 下記に香典のお金に関するマナーをご紹介します。 |
| 新しいお札はダメ。汚すぎるお札もダメ ・あまりにも汚いお札は失礼にあたりますが、新しい札もだめ(新札・ピン札もダメ)。新しいお札をあらかじめ用意して亡くなるのを待っていたようだとされます |
| お札の向きをそろえる ・お札の向きを揃えるのがマナーです。 |
・お札にも表と裏があります。 不祝儀袋に入れる際にはお札の向きをそろえるようにします。 右のイラストを参照して下さい。袋の表側に、お札の表側が来るようにします。 |
| (2)香典のお金・お札の入れ方と向き | |
| 香典に関してはお札の入れ方に明確な決まりはないようですので、一般論として不祝儀袋の入れ方を紹介します。 不祝儀袋に関しては、お札の裏が、表に向くように入れるのが慣例のようです(顔を伏せるという意味があるようです)。 下記のイラスト見本では、上段が丁寧な形です。 金額が多い時の袋が上段です。 |
|
正式包み:上包み+中包みのとき |
|
 |
|
不祝儀袋+中袋のとき |
不祝儀袋だけ |
 |
 |
スポンサードリンク
5. 香典とふくさ、袱紗の使い方
不祝儀袋を渡す時の正式なマナーは、袱紗(ふくさ)を使います。
袱紗は色によって用途も異なって来ますので、新しく買う場合には色にも注意しましょう。
| (1)袱紗の用途と色 | ||||||||
| ふくさに用いられる主な色と用途をご紹介します。 下記以外にも様々な色のものがありますが、暖色系の明るい色は慶事用、寒色系の沈んだ色は弔事用と覚えておきましょう。 紫色はどちらにも使えるとされています。 |
||||||||
用途 |
色 |
|||||||
| お祝い事・慶事用 | ||||||||
| 赤 | オレンジ | ふじ | 桃 | えんじ | 金 | ローズ | 紫 | |
| お悔やみ事・弔事用 | ||||||||
| 紺 | 深緑 | 灰緑 | 緑 | うぐいす | 灰青 | グレー | 紫 | |
| ・紫色は慶事、弔事のどちらにも使えるため、一枚あると便利です。 袱紗は四角形ですが、不祝儀袋などを包みやすいように略式として金封の形になっているものも市販されています。 下記(2)でご紹介します。 |
||||||||
| (2)袱紗の種類(ふくさ) | |
| ・袱紗(ふくさ)はもとは中央の見本のような四角い形でしたが、現在では使いやすい金封タイプや、台付きなども販売されています。 | |
| 金封タイプの袱紗(ふくさ) | 台付き袱紗(ふくさ) |
 |
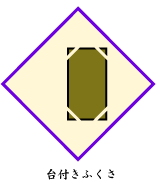 |
| 袱紗・爪付き袱紗(ふくさ) | |
 |
|
| ※弔事の際の袱紗の包み方、使い方については「袱紗(ふくさ)」のページで詳しく説明します>>> | |
スポンサードリンク