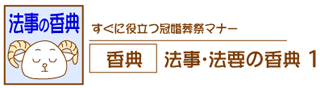
| ………このページの内容……… | |
|---|---|
| ▼1. 香典とは? 香典はいつ持参するの? | |
| ▼2. 香典袋の書き方 香典の表書きとのし袋 | |
| ▼3. 中袋・中包みの書き方 | |
| ▼4. お金の入れ方 お金の包み方 次のページ | |
| 新札は用いない?お札の向きを揃える | |
| ▼5. 香典の金額の相場とめやす 次のページ | |
| ▼6. 受付でのマナーと香典の出し方・渡し方 次のページ | |
| ※ 一周忌法要の流れとマナーは別ページへ>>> | |
| [関連ページ](以下は別ページ) | |
| ・法事の香典は薄墨か濃墨か? 法事の香典は新札か?>>> | |
| ・香典の入れ方、包み方>>> | |
| ・香典の入れ方(中袋がない時ほか)>>> | |
| ・香典の渡し方 通夜,葬儀,告別式>>> | |
| ・香典の渡し方 法事,法要>>> | |
| ・香典の渡し方 後日>>> | |
| ・香典の渡し方 袱紗の使い方>>> | |
| ・法要 法事 回忌 早見表>>> | |
| ・法事・法要いつまで?>>> | |
|
| (1)香典とは |
| ・香典とは故人に対する供養の気持ちを表わし、故人の冥福を祈り供養をするために捧げるものです。本来は花や線香なども供物として備えられますが、現代では香典という名称を使う場合には主として現金をさします。 香典の他に、香料とも言われます。 |
| (2)通夜・葬儀の香典 |
| 香典を持参する時期 |
| ・香典は通夜または葬儀のいずれかに持参します。[詳細はこちら] ・通夜・葬儀のときと、法要とではのし袋の表書きが異なりますので注意してください。 |
| (3)法要の香典 |
| 香典を持参する時期 |
| ・初七日をはじめとし、四十九日までの間、法要は七日ごとにあります。また、その後も、百箇日、一周忌、三回忌…と続きます。 香典を持参するのは、主な法要のみで、他は遺族による焼香やお供えが行われます。 ・主な法要 |
主な法事・法要の名称と日数の数え方 |
|
| 法要の名前 | 時期 |
| 追善法要 | |
| 初七日 (しょなぬか) |
・初七日は、本来は亡くなってから7日目に行われるのですが、最近は遺族や知人の日程に配慮し、葬儀当日に、火葬場から戻ってきてから遺骨を迎える儀式(還骨勤行=かんこつごんぎょう)と合わせて行われることが多いようです。 |
| 四十九日 (しじゆうくにち) |
49日目 |
| 追悼法要 | |
| 初盆・新盆 (はつぼん) ( にいぼん) |
(死後の日数とは関係なく)初盆の法要は、四十九日を過ぎてから初めてのお盆に行います。四十九日よりも前にお盆が来た場合には、翌年に初盆の法要を行います。 お盆の時期は地域によって異なりますが、旧暦のお盆なら7月。一般的には8月の13日〜16日です。 |
スポンサードリンク
主な法事・法要の名称と日数の数え方 つづき |
|
| 法要の名前 | 時期 |
| 年忌法要 | |
| 一周忌 (いっしゅうき) | 満1年目 |
| 三回忌 (さんかいき) | 満2年目 |
| 七回忌 (ななかいき) | 満6年目 |
| この間、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌といった具合に、年忌法要があります。遺族のみで行われます。 | |
| 三十三回忌 (さんじゅうさんかいき) | 満32年目 |
2.香典袋の書き方 香典の表書きとのし袋
香典袋の書き方は宗教によって異なります。必ず喪家(喪主)の宗教にあった表書きの香典を持参します。
下記に書き方の見本をご紹介しますので、香典用ののし袋を買い求める際(のし袋の選び方)の参考になさってください。
また、もし通夜や葬儀に出席できず郵送で送る場合は弔電を打ち現金書留で香典を送ります。香典の送り方については別
ページでご説明しておりますのでご参照ください。
※別ページ…[香典の郵送のしかた]
※次ページ…[受付での香典の出し方・渡し方]
| A.仏教の場合の香典の書き方 | |
| (1)通夜・葬儀の香典袋の書き方と見本 | |
| ・通夜・葬儀のときと、法要とではのし袋の表書きが異なりますので注意してください[詳細はこちら]。 | |
| (2)法要の香典袋の書き方 | |
| 法事の香典 | 香典の書き方 |
  |
[表書き] ・仏教の場合の熨斗の表書きは「御仏前」「御佛前」「御香料」などです。 「御仏前」という表書きは四十九日以降に使用される表書きで、仏教以外には用いません。 [のし袋の選び方と水引き] ・黄白、双銀または黒白の水引き ・結び切り(左の画像見本のように、堅く結んで切ったシンプルなもの)またはあわじ結び(あわび結びとも言います。 結び目の形は上記(1)の御霊前の見本画像で紹介しています) ・蓮(はす)の花の絵がついているものは、仏教専用です。 [墨] ・薄墨で書くのは四十九日までとされており、最近は四十九日以降の法事法要では黒い墨を用いるようです。 ※薄墨には、訃報に接して悲しみの涙で墨が薄くなったという意味があるようです。 [名前] ・会葬者の氏名をフルネームで書きます。会社の名前で香典を出す場合の書き方例はこちら[B.香典の名前の書き方] |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
| B.香典の下段 名前の部分の書き方 つづき | ||||
| (2)法事・法要の香典袋の書き方と見本 つづき | ||||
| ●会社名義で香典を出す | ||||
|
||||
| ●部署やグループ名で香典を出す | ||||
|
||||
スポンサードリンク
| C.キリスト教の場合の香典の書き方 | |
| (1)通夜・葬儀の香典袋の書き方と見本 | |
| ・キリスト教の場合の熨斗の表書きについては、[通夜・葬儀の香典]へ | |
| (2)追悼ミサ、記念ミサなどの香典袋の書き方 | |
| 法要の香典 | 香典袋の書き方 |
  |
・キリスト教でも、法事に該当する儀式があります。 カトリックでは、一ヶ月目に「追悼ミサ」一年目に「記念ミサ」など。 プロテスタントでは、一ヶ月目、1年目の「昇天記念日」に「記念集会」など。 [表書き] 「御花料」(プロテスタント) 「御ミサ料」(カトリック)などです。 [のし袋の選び方と水引き] ・十字架の絵が付いたものまたは白い封筒もしくは不祝儀用の熨斗袋。 ・蓮(はす)の花の絵がついているものは、仏教専用ですので使わないように注意してください。 [墨] ・キリスト教では忌明けという考え方がないため、墨の色に関する細かいしきたりや作法がありません。一ケ月目の追悼ミサ以降は黒い墨でも良いでしょう。 [名前] ・会葬者の氏名をフルネームで書きます。会社の名前で香典を出す場合の書き方例はこちら[B.香典の名前の書き方] |
| 直接手渡しでお届け 送料無料 当日配達も可能 |
| D.神道(神式)の場合の香典の書き方 | |
| (1)通夜・葬儀の香典袋の書き方と見本 | |
| ・神式(神道)の場合の熨斗の表書きについては、[通夜・葬儀の香典]へ | |
| (2)霊祭、式年祭などの香典袋の書き方 | |
| 法要の香典 | 香典袋の書き方 |
  |
・神式でも、法事に該当する儀式があります。 主なものは「十日祭」「五十日祭」「百日祭」など。 一年目からは式年祭と呼ばれる儀式があり、「一年祭」「三年祭」…など神職を招いたりして霊祭が行われます。 ・神式(神道)の場合の熨斗の表書きは 「御玉串料」「御榊料」「御神饌料」などです。 「御霊前」という表書きは宗教を問わずに使えるとされていますが、蓮の絵が付いているものだけは、仏教専用の熨斗袋なので、神式の葬儀には用いないように注意してください。 [のし袋の選び方と水引き] ・不祝儀用の熨斗袋。 ・もし水引きのあるものを使う場合には黒白または双銀の水引き ・結び切りまたはあわじ結び(あわび結びとも言います) ・蓮(はす)の花の絵がついているものは、仏教専用ですので使えません。 [墨] ・霊祭、式年祭については墨の色に関する細かい規定・作法がありません。薄墨も使われますが、五十日祭以降は黒い墨でも良いでしょう。 [名前] ・会葬者の氏名をフルネームで書きます。会社の名前で香典を出す場合の書き方例はこちら[B.香典の名前の書き方] |
スポンサードリンク
3.中袋・中包みの書き方
香典袋には、中袋または中包みと呼ばれる袋が入っています。
中袋(または中包み)には、中に入れたお金の金額を書き、会葬者の住所氏名などを書きます。
市販されているものの中には、「金額を書く欄」「住所氏名そ書く欄」が決められているものもあるようです。
| 香典の中袋・中包みの書き方 | |||||||||||||||||||||||||
| 筆記用具 | |||||||||||||||||||||||||
| ・筆を使うのが正式な作法ですが、筆ペンや、ペンでも良いでしょう。黒インクのものを用います。薄墨でなく黒で書きます。 | |||||||||||||||||||||||||
| 中に入れる金額 | |||||||||||||||||||||||||
| ・死や苦を連想させる数字として(四、九)がつく金額は避けるのが一般的です。少額の場合は連名で香典を出すなどして、 3千円、5千円、1万円、2万円、3万円、5万円、10万円、20万円、30万円など、キリの良い金額にします。 ・香典の金額の相場については、次のページの項5「香典の金額の相場とめやす」にて |
|||||||||||||||||||||||||
| 香典の金額の書き方 | |||||||||||||||||||||||||
| 香典の中包み(または中袋)に金額にを書く場合、難しい漢字を使うのが慣例です。 「一」「二」などの文字は後で線を書き加えるだけで簡単に数字の改ざんができてしまうため、数字の改ざんができないようにという考え方からきています。 なお、最近では金額を書く欄が横書き用で、アラビア数字で書く場合もあるようです。 (例:金30,000円也) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 中袋の書き方 | |||||||||||||||||||||||||
・香典の中袋の書き方です。下記のサンプル画像をご覧ください。
|
|||||||||||||||||||||||||
スポンサードリンク