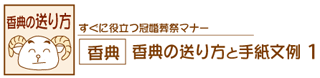
| ………このページの内容……… |
|---|
| ▼1-1. 通夜、葬儀・葬式、法事に出席できないとき |
| ▼1-2. 訃報を後で知った、死亡したことを他の人から聞いたとき |
| ▼2. 香典袋の書き方 香典の表書きとのし袋 |
| ▼3. 香典の郵送のしかた |
| ▼4. お悔やみの手紙の例文・文例 次のページへ |
| ▼5. お礼状(四十九日を過ぎてから届いた香典へ) 次のページへ |
| ※参考ページ…不祝儀袋(中袋なし・中袋がない時)別ページへ |
| [関連ページ] |
| ・香典の入れ方、包み方>>> |
| ・香典の入れ方(中袋がない時ほか)>>> |
| ・中袋なしの香典の書き方と裏面>>> |
| ・香典の渡し方 通夜,葬儀,告別式>>> |
| ・香典の渡し方 法事,法要>>> |
| ・香典の渡し方 後日>>> |
| ・香典の渡し方 袱紗の使い方>>> |
| ・お悔やみの言葉メール 友人、親戚、同僚、上司>>> |
| ・お悔やみの電話の仕方 いつする?例文とマナー>>> |
1-1. 通夜、葬儀・葬式、法事に出席できないとき
香典とは、故人に対する供養の気持ちを表わすものであり、線香や花の代わりとして通夜、葬儀・葬式、法要の際に持参します。
しかし、どうしても出席できないときには、弔電を打ち、香典を送ります。
| (1)通夜、葬式・葬儀に参列できないとき | |
| ① 企業をはじめとする職場において、社員の家族が亡くなった場合、本来であれば直属の上司などが通夜または葬儀に参列しますが、通夜や葬儀が遠方で行われる場合、「弔電を打ち、香典を送る」あるいは「弔電を打ち、供花を贈る」などの手配をします。 ※まれに、社員が葬儀を終えて出社してからお悔やみを述べ、香典を手渡すこともあります。しかし、本来香典は故人の霊前にお供えするものであり、一日も早く送る方が良いでしょう。 ※弔電の文例はこちらでご紹介しています[弔電の文例] |
|
| ② やむを得ない理由で、親しい人やお世話になった人の(またはその家族の)、通夜、葬儀・葬式、に参列できない場合にも、お悔やみの手紙を添えて香典を贈ります。
※通夜、葬儀・葬式の場合は、「お悔やみの手紙+香典」だけでなく、弔電を打ち、香典を送ることもあります。 ※弔電の文例はこちらでご紹介しています[弔電の文例] |
|
| (2)法事・法要に参列できないとき | |
| ・やむを得ない理由で、親しい人やお世話になった人(またはその家族)の、法事・法要に参列できない場合にも、お悔やみの手紙を添えて香典を贈ります。
※本来、法事の場合は案内状を受け取ったらできるだけ出席するのがマナーですが、どうしても出席できない場合に香典を送ります。ただし法事の場合は前もって日程がわかるため、弔電なしで、お悔やみの手紙に香典を添えて送ります。 |
スポンサードリンク
1-2. 訃報を後で知った、死亡したことを他の人から聞いた、
喪中はがきではじめて訃報を知ったとき
自分の身の回りでも意外と多いのが、「喪中はがきが届いてから、訃報を初めて知った」というケースです。
| (1)訃報を後で知った時、あるいは、死亡したことを他の人から聞いた時など | |
|
・自分の身の回りでも意外と多いのが、「喪中はがきが届いてから、訃報を初めて知った」というケースです。 特に学生時代の友人(またはその家族)の訃報などは、社会人になってからのお互いの生活の拠点が離れていると知る機会も少なくなってきます。 訃報を知った時点で構いませんので、故人とのおつき合いの深さにより、お悔やみの手紙を出したり、香典を送ったりします。お花を贈るというのも良いでしょう。もちろん、直接お悔やみに伺うことができれば、まずはお悔やみの手紙を送り、日を改めてご焼香(焼香は仏教のみ)に伺うのも良いと思います。 なお、香典を送る場合の表書きは、故人が亡くなってからどのくらい経っているのかによって変わってきます。仏教の場合の御霊前の表書きなどのように、使える時期に制限があるものもあります。 ※御霊前はいつまで使える?>> (※線香を贈る方もいらっしゃるようですが、線香は仏教のみに限られますので、喪家の宗教を必ず確認するようにしてください。宗教がわからない時には、香典、お花などが無難です。) |
2.香典袋の書き方 香典の表書きとのし袋
香典袋の書き方は宗教によって異なります。必ず喪家(喪主)の宗教にあった表書きの香典を持参します。
下記に書き方の見本をご紹介しますので、香典用ののし袋を買い求める際(のし袋の選び方)の参考になさってください。
また、もし通夜や葬儀に出席できず郵送で送る場合は弔電を打ち現金書留で香典を送ります。香典の送り方については別
ページでご説明しておりますのでご参照ください。
※別ページ…[香典の郵送のしかた]
| ※香典を送る場合の香典袋 |
| ・香典を送る場合には、香典袋を現金書留で送るのが正式なマナーです。 ・通常、現金を熨斗袋に入れ現金書留専用の封筒に、香典袋ごと入れ、お悔やみの手紙を添えて郵送します(※なお、熨斗袋の書き方はこのすぐ下で説明しています) 。 ・細かいことですが、郵送に使うのし袋は水引きの部分も印刷されているようなフラットなタイプ(平たんなのし袋)の方が使いやすいです。もちろん、直接香典を持参する場合には、のし袋は中身の金額にふさわしいものを使うのが本来のマナーですが、郵送する際に現金書留用の封筒に入れにくいので注意して下さい。 (もし熨斗袋が大きくて現金書留専用の封筒に入らない場合、現金書留専用の封筒以外でも現金を送ることができますが、中身の補償を受けたいのであれば、窓口に申し出て必要な料金を支払い、所定の封緘(ふうかん)印などを行います。) |
| A.仏教の場合の香典の書き方 につづく |
スポンサードリンク
| A.仏教の場合の香典の書き方 | |
| (1)通夜・葬儀の香典袋の書き方と見本 | |
| 香典の書き方 | |
・仏教の場合の熨斗の表書きは「御霊前」「御香料」などです。 中でも最も一般的なのは「御霊前」です。 表書き注意ポイント/御霊前はいつまで? 仏教の場合の御霊前という表書きは四十九日(忌明け)より前の法要で用いられます。 [のし袋の選び方と水引き] ・黒白または双銀の水引き ・結び切りまたはあわじ結び(あわび結びとは、左の見本画像のように、結び切りよりも結び目が豪華でアワビのような形になったもの。あわび結びとも言います) ・蓮(はす)の花の絵がついているものは、仏教専用です。 [墨] ・薄墨を用います。悲しみの涙で文字が滲んでいるという気持ちを表わすとされています。 [名前] ・会葬者の氏名をフルネームで書きます。 ・社員本人、社員の家族、あるいは取引先の社員にご不幸があった場合、会社として香典を出すことがあります。 会社の名前で香典を出す場合の書き方例はこちら[B.香典の名前の書き方] |
|
| (2)法要の香典袋の書き方 | |
| 香典の書き方 | |
・仏教の場合の熨斗の表書きは「御仏前」「御佛前」などです。 「御仏前」という表書きは四十九日以降に使用される表書きで、仏教以外には用いません。 [のし袋の選び方と水引き] ・黄白、双銀または黒白の水引き ・結び切り(左の画像見本のように、堅く結んで切ったシンプルなもの)またはあわじ結び(あわび結びとも言います。結び目の形は上記(1)の御霊前の見本画像で紹介しています) ・蓮(はす)の花の絵がついているものは、仏教専用です。 [墨] ・薄墨の場合が多いようです。最近では黒い墨を用いることもあるようです。 [名前] ・会葬者の氏名をフルネームで書きます。会社の名前で香典を出す場合の書き方例はこちら[B.香典の名前の書き方] |
スポンサードリンク
| (1)通夜・葬儀の香典袋の書き方と見本 |
| ●個人で香典を出す |
・仏教の場合、通夜、葬儀、初七日は「御霊前」(墨は薄墨)、四十九日以降の法事・法要は「御仏前」です。 ・中央に会葬者の氏名をフルネームで書きます。 ・夫の出張中に妻が代理で会葬する場合には、夫の氏名の左下に小さく「内」と書きます。受付の会葬者名簿にも同じように夫の氏名の左下に小さく「内」と書きます。 |
| ●夫婦で会葬する |
|
| ●二人で香典を出す(数人が連名で出す) |
三名の場合は中心に一名の氏名を書き、その左右両側に一名ずつ書きます。 人数が4名以上になる場合には代表者名を中央に書き「他5名」などと左下に書き添えても良いでしょう。 職場などで連名で香典を出す場合は、社名を一番右に書いたあと、役職が上の人が一番右になります。 |
| ●会社名義で香典を出す |
会社で香典を出す場合には、社名ではなく代表者の氏名を書きます。 左の見本画像のように、中央に社長の氏名が来るように、その右側に書く会社名の配置を決めます。 ・会社などにおいて部下が代理で会葬する場合には、上司の氏名の左下に小さく「代」と書きます。受付の会葬者名簿にも同じように上司の氏名の左下に小さく「代」と書きます。 ・上司の代理で会葬する場合、上司の名刺を預かって行きます。受付では上司の名刺の右上に「弔」と書き、縦書きの名刺の場合は左端、横書きの場合は下端に「上司の代わりに会葬させて頂きます。佐藤一夫」と会葬した人の氏名を書いて受付に渡します。 |
| ●部署やグループ名で香典を出す |
中に紙を入れ、香典を出した人の氏名と金額、住所、連絡先を書き添えると遺族の側でもお礼状やお返しの手配の際に困りません。 同僚たちで香典をまとめる場合、トータルの金額は端数がないようにします。 (□万円、□千円はOK。□万□千円はNG。また、4、9などの数字は死、苦を連想させるため好ましくありません。) ・(これは必須ではないのですが)部署名で香典を出す場合、代表者のみが会葬するのであれば、できれば受付では名刺の右上に「弔」と書き、縦書きの名刺の場合は左端、横書きの場合は下端に「○○部を代表して会葬させて頂きました」と書いて受付に渡すと丁寧ですし、遺族も香典返しやお礼状(お礼の手紙)などの手配の際に宛先がわかりやすくなります。 |
スポンサードリンク
| C.キリスト教の場合の香典の書き方 | ||
| (1)通夜・葬儀の香典袋の書き方と見本 | ||
| 通夜・葬儀の香典の書き方 | ||
・キリスト教の場合の熨斗の表書きは 「御花料」(プロテスタント) 「 御ミサ料」(カトリック)などです。 「御霊前」という表書きは宗教を問わずに使えるとされていますが、蓮の絵が付いているものだけは、仏教専用の熨斗袋なので、キリスト教式の葬儀には用いないように注意してください。 [のし袋の選び方と水引き] ・十字架の絵が付いたものまたはまたは白い封筒もしくは不祝儀用の熨斗袋。 ・もし水引きのあるものを使う場合には黒白または双銀の水引き ・結び切りまたはあわじ結び(あわび結びとも言います) ・蓮(はす)の花の絵がついているものは、仏教専用ですので使えません。 [墨] ・薄墨を用います。悲しみの涙で文字が滲んでいるという気持ちを表わすとされています。 [名前] ・会葬者の氏名をフルネームで書きます。会社の名前で香典を出す場合の書き方例はこちら[B.香典の名前の書き方] |
||
| (2)追悼ミサ、記念ミサなどの香典袋の書き方 | ||
| 香典袋の書き方 | ||
| ・キリスト教でも、法事に該当する儀式があります。 カトリックでは、一ヶ月目に「追悼ミサ」一年目に「記念ミサ」など。 プロテスタントでは、一ヶ月目に「昇天記念日」など。 [表書き] 「御花料」(プロテスタント) 「 御ミサ料」(カトリック)などです。 [のし袋の選び方と水引き] ・十字架の絵が付いたものまたは白い封筒もしくは不祝儀用の熨斗袋。 ・蓮(はす)の花の絵がついているものは、仏教専用ですので使わないように注意してください。 [墨] ・キリスト教については墨の色に関する細かい規定がありません。薄墨が無難ですが、なければ黒い墨でも良いでしょう。 [名前] ・会葬者の氏名をフルネームで書きます。会社の名前で香典を出す場合の書き方例はこちら[B.香典の名前の書き方] |
スポンサードリンク
| D.神道(神式)の場合の香典の書き方 | ||
| (1)通夜・葬儀の香典袋の書き方と見本 | ||
| 香典の書き方 | ||
・神式(神道)の場合の熨斗の表書きは 「御玉串料」「御榊料」「御神饌料」などです。 「御霊前」という表書きは宗教を問わずに使えるとされていますが、蓮の絵が付いているものだけは、仏教専用の熨斗袋なので、神式の葬儀には用いないように注意してください。 [のし袋の選び方と水引き] ・不祝儀用の熨斗袋。 ・もし水引きのあるものを使う場合には黒白または双銀の水引き ・結び切りまたはあわじ結び(あわび結びとも言います) ・蓮(はす)の花の絵がついているものは、仏教専用ですので使えません。 [墨] ・薄墨を用います。悲しみの涙で文字が滲んでいるという気持ちを表わすとされています。 [名前] ・会葬者の氏名をフルネームで書きます。会社の名前で香典を出す場合の書き方例はこちら[B.香典の名前の書き方] |
||
| (2)霊祭、式年祭などの香典袋の書き方 | ||
| 香典袋の書き方 | ||
| ・神式でも、法事に該当する儀式があります。 主なものは「十日祭」「五十日祭」「百日祭」など。 一年目からは式年祭と呼ばれる儀式があり、「一年祭」「三年祭」…など神職を招いたりして霊祭が行われます。 ・神式(神道)の場合の熨斗の表書きは 「御玉串料」「御榊料」「御神饌料」などです。 「御霊前」という表書きは宗教を問わずに使えるとされていますが、蓮の絵が付いているものだけは、仏教専用の熨斗袋なので、神式の葬儀には用いないように注意してください。 [のし袋の選び方と水引き] ・不祝儀用の熨斗袋。 ・もし水引きのあるものを使う場合には黒白または双銀の水引き ・結び切りまたはあわじ結び(あわび結びとも言います) ・蓮(はす)の花の絵がついているものは、仏教専用ですので使えません。 [墨] ・霊祭、式年祭については墨の色に関する細かい規定がありません。薄墨が無難ですが、なければ黒い墨でも良いでしょう。 [名前] ・会葬者の氏名をフルネームで書きます。会社の名前で香典を出す場合の書き方例はこちら[B.香典の名前の書き方] |
スポンサードリンク
3.香典の郵送のしかた(2018.1.25加筆修正)
・通常、現金を熨斗袋に入れ現金書留専用の封筒に、香典袋ごと入れ、お悔やみの手紙を添えて郵送します。ここでは、現金書留専用封筒で郵送する場合の送り方についてご説明します。
郵便局に行く前に、香典袋とお悔やみの手紙と印鑑(なくても可)を用意します。
| 1.香典袋(熨斗袋)に現金を入れる | |
|
・まずは、現金を香典袋に入れます。この時使うのし袋は、水引きの部分も印刷されているようなフラットなタイプ(平たんなのし袋)の方が使いやすいです。もちろん、直接香典を持参する場合には、のし袋は中身の金額にふさわしいものを使うのが本来のマナーですが、郵送する際には水引きが立派なタイプは現金書留用の封筒に入れにくいので注意して下さい。 フラットで厚みのないのし袋の方が一般的に「重量」「厚み」などの項目において郵送料金も安くなる可能性が高いというメリットもあります。 ・ お札は新札は不可です。あまりシワシワのものや汚れたお札も失礼にあたりますので、もし新札しかない場合には、一度お札を二つ折りにし、開いてから入れます。また、2枚以上のお札を入れる時には、お金の向きを揃えて入れます。 ※エクスパックの利用について>振り込め詐欺で使われたイメージがあり、印象があまり良く無かったエクスパックは、平成26年3月31日(2014年3月31日)までで取扱が終了されました。 |
|
| 2.郵便局で現金書留封筒を買う | |
現金書留封筒(現金書留専用封筒) |
|
郵便局の窓口で販売しています。21円/枚 現金をそのまま入れるサイズのものと、香典袋が入るくらいの(少し大きめの)サイズがあります。「香典袋が入る大きさのものを」と指定して購入してください。 いずれの大きさの封筒も21円です。 |
|
| 3.封筒に必要事項を記入する (現金書留封筒では、宛先、差出人、金額欄などが複写式になっているので、ボールペンなどで強く記入します) |
|
| 宛名・宛先 | |
| 本来のマナーでは、香典の宛先は喪主あてとなります。しかし喪主と全く面
識がない場合には、あなたとお付き合いのある友人・知人あてにお悔やみの手紙を添えて送ります。 ※現金書留封筒では宛名の欄は「お受取人」となっています。 |
|
| 差出人住所氏名 | |
| 個人で送る場合には自分の住所氏名となりますが、会社で送る場合には、会社名ではなく、代表者名(社長名など)で送ることになります。電話番号も忘れずに記載します。 | |
| 損害要請額 | |
| 現金書留の場合、50万円まで損害要償額を申し出ることができます。但し、中身の金額を超えて申し込むことはできません。 (一般書留の場合は500万円まで。一般書留で送ることができるものは、約款で「貴重品」と定められた貴金属などをさし、現金は「現金書留」で送る必要があります) 損害要償額の申し出がないときは、現金書留の損害要償額は1万円となります。 |
|
| 4.香典と、お悔やみの手紙を入れて封緘する | |
| 封筒に中身を入れて封緘(「封緘」読み方=ふうかん) | |
| ・現金書留封筒に、香典と、お悔やみの手紙を入れて封緘します。 ・この場合、香典はのし袋に入れてから同封しますが、手紙の方は簡単にお悔やみの言葉を一言添えるという程度であれば便箋のまま入れても失礼にはあたりません。 もしも手紙を封筒に入れてから同封する場合には、手紙を入れる封筒はシンプルな一重の封筒にします。二重封筒のタイプはNGです(「重なる」=不幸が重なるとして嫌われます。) ・現金封筒(現金書留専用封筒)について…現金書留封筒は二重構造になっています。中身を入れたのち、最初に内側の袋の封をしたあと、外袋の封をします。最後に封緘(※)をします。 現金書留封筒には、封緘紙がついているものもあります。 [ポイント!] 郵便局に香典と手紙を持って行き、その場で中に入れると、やり方がわからないときには親切に教えてくれます。 ※封緘=「ふうかん」と読みます。封筒などを閉じることをさしますが、封をした証しとして、封緘紙を貼って封をしたり、割り印を押したり、サインをしたりします。 封緘紙とは=ふうかんし。切手のような大きさの薄い紙で、不正な開封を防ぐために貼るもの。一度封をしたあとで第三者が不正に剥がすと破れ、開封されたことがわかる。 割り印とは=蓋と本体との両方にかかるように、印鑑を押すことです。普通 の印鑑で構いません。 |
|
| 5.料金を支払い、「控え」をもらう。 | |
| 窓口で支払う料金は、「封筒代」「郵便料金」「書留料金」の合計となります。 (下記の表のA+B+C)です。 もし、速達で送る場合には、更に「速達料金」(表D)が加算されます。 代金を支払うと、引き受け番号を記載した控えを渡してくれます。香典が届いたというお礼の連絡があるまで、万一の送付事故に備えて、控えを保存しておきましょう。 |
|
スポンサードリンク
|
[現金書留を利用する場合に必要な費用(金額)] |
|||||
香典を現金書書留で送る場合に必要な料金 = A + B + C |
|||||
| 以下の金額表示は 2017年06月変更以降のもの 2018年1月現在 | |||||
| 封筒代 | |||||
| A現金書留封筒 | |||||
郵便局の窓口で「現金封筒」「現金書留封筒」「現金書留専用風等」として販売しています。21円/枚 |
|||||
| 書留郵便料金 | |||||
| B郵便料金 | |||||
| ●重量に応じて料金が変わります。 ●重さ50gを超えるものは定形外郵便物となります。 |
|||||
| 定形外郵便物の料金 | 規格内 | 規格外 | |||
| 50g以内 | 120円/通 | 200円/通 | |||
| 100g以内 | 140円/通 | 220円/通 | |||
| 150g以内 | 205円/通 | 290円/通 | |||
| 250g以内 | 250円/通 | 340円/通 | |||
| 500g以内 | 380円/通 | 500円/通 | |||
| 1kg以内 | 570円/通 | 700円/通 | |||
| 2kg以内 | 取扱いなし | 1,020円/通 | |||
| 4kg以内 | 1,330円/通 | ||||
| C書留料金 | |||||
| ●損害要償額に応じて料金が変わります | |||||
| ・損害賠償額が1万円までの場合 | 430円/通 | ||||
| 損害賠償額が1万円を超える場合には、5,000円ごとに10円が加算されます | 例)2万円のとき |
|
450円/通 | ||
| 例)3万円のとき |
|
470円/通 | |||
| 例)5万円のとき |
|
510円/通 | |||
| 例)10万円のとき |
|
610円/通 | |||
|
|||||
| オプション | |||||
| D速達料金 | |||||
| ●もし速達で送る場合は、速達料金が加算されます | |||||
| 250gまで | 上記+280円/通 | ||||
| 1kgまで | 上記+380円/通 | ||||
| 4kgまで | 上記+650円/通 | ||||