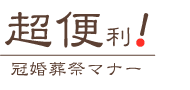ここでは納骨式の流れと遺族や親族など参列者の服装について解説します。 納骨式を行う時期、及び納骨式の準備については別ページへ>>> |
3.納骨式の流れと挨拶
下記に宗教ごとに納骨式の流れをご紹介します。地方や宗派によっても異なりますので、一般例としてご参照ください。
ここでは代表的な例として、仏教、キリスト教、神道の納骨式の流れをそれぞれ説明します。
| 仏教「納骨式の流れ」 | |
|---|---|
| 式次第 | 仏教の納骨式解説 |
| 下記は、忌明け法要に引き続いて納骨式を行う場合の進行例です。 | |
| [忌明け法要] | |
| 納骨式に先立ち、忌明けの法要(四十九日の法要)を行います。 | |
| 1.施主の挨拶 | |
| 施主が、忌明けの法要が終わったことのお礼を述べ、参列者に墓地への移動を促します。 [※施主の挨拶の文例・例文] 皆様、おかげさまで無事に忌明けの法要を済ませることができました。
引き続き納骨式(または納骨法要)を予定しておりますので、ご参列いただける方は順次墓地の方へ移動をお願いいたします。 一旦、入り口横で集合してから一緒に移動したいと思いますのでご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 [下記は付け足し文の例1] この後、別室にて簡単な茶菓を用意いたしております。納骨式に参列されない方もどうぞ一息ついて頂き、ゆっくりと故人を忍んで頂ければと存じます。 本日はまことにありがとうございました。 [下記は付け足し文の例2] なお、本日は墓地の日差しが大変強くなっており、厳しい暑さが予想されます。ご気分のすぐれない方はどうぞご無理をなさらず、控え室でお休み頂ければと存じます。宜しくお願い申し上げます。 |
|
| 2.お墓の周辺をきれいにする | |
| お墓の周りをきれいにする(雑草を取る)。 墓石に水をかけて浄める。 お花(供花)や、お供え物を置く。 [お供え物の例]…お菓子、果物、お酒など。 但し、お供え物は納骨式が終わった後で持ち帰るように指示されるケースが増えていますので、持ち帰りのできるものにします。またお供え物を置くスペースの広さにも配慮しましょう。また、お酒をお供えすること自体が禁止されている墓地もあります。 ※参考…納骨式の準備>>> |
|
| 3.僧侶による読経 | |
| 墓前で僧侶による読経が行われます。 | |
| 4.参列者による焼香 | |
| 遺族が順番に焼香を行います。施主が最初に行い、他の遺族は故人と縁が深かった人から順に焼香します。 | |
| 5.納骨・埋骨 | |
墓地の場合には、お墓のカロートをあけてもらい、施主が遺骨を納骨します(骨壷のまま入れるか、納骨袋で納めるのかは事前に要確認)。 |
|
| 6.僧侶による読経 | |
| 納骨ののち、再び僧侶による読経が行われます。 | |
スポンサードリンク
| 仏教「納骨式の流れ」つづき | |
| 7.参列者による焼香 | |
| 再び遺族が順番に焼香を行います。 | |
| 8.施主による挨拶 | |
施主が、納骨式が終わったことのお礼を述べ、会食(お斉)がある場合には参列者に会場への移動を促します。 [※施主の挨拶の文例・例文] おかげさまで無事に納骨を済ませることができました。 ありがとうございました。故人もようやく落ち着いたことと思います。 この後、別会場にて粗宴を用意いたしております。入り口脇にお集まり頂いたのちに、バスでの移動となります宜しくお願い申し上げます。 本日はお忙しい中をお集りいただきまして誠にありがとうございました。 |
|
| 上記のように忌明けの法要のあとで納骨式を行うのが一般的ですが、この日に納骨を行わない場合でも遅くとも死後一年以内に納骨をします。 [納骨式の案内] 例えば四十九日の法要を行う際などに、合わせて案内をするのが良いでしょう。案内状の文例を、別ページで紹介します。>>> [開眼法要•開眼供養] 新しいお墓を用意した場合には、開眼供養あるいは開眼法要という儀式を行います。普通は納骨式と同じ日に行うこともできますのでお寺に相談してみてください。 [浄土真宗の納骨式] 浄土真宗の納骨式の流れもだいたい上記と同じです。もし新しいお墓を用意した場合には、開眼法要にあたる「建碑法要(けんぴほうよう)」という儀式を行います。墓前にはお線香、お花、お供物などを持参します。納骨式の準備のページをご参照ください。>>> |
|
| キリスト教「納骨式の流れ」 | |
|---|---|
| 式次第 | キリスト教の納骨式解説 |
| 下記は、カトリック教会において追悼ミサののち納骨式を行う場合の進行例です。 | |
| [追悼ミサ] | |
| 納骨式に先立ち、教会にて追悼ミサを行います。 | |
| 1.墓地への移動 | |
| 教会の係員または聖職者などが、墓地への移動を案内します。 | |
| 2.墓地にて聖職者による聖書朗読 | |
| 聖職者により聖書が朗読されます。この例のように別会場で追悼ミサが行われた場合には、聖書朗読が省略されることもあります。 | |
| 3.聖歌斉唱、賛美歌斉唱 | |
| 参列者全員で賛美歌を歌います。 | |
| 4.納骨・埋骨 | |
遺骨を墓地に納めます。施主の手によって納めることが多いようです。 |
|
| 5.献花 | |
| 参列者による献花が行われます。 | |
| 6.聖職者による祈りの言葉 | |
| 聖職者により祈りの言葉が朗読されます。 | |
| 上記のようにカトリックでは一ヶ月後の命日に行われる追悼ミサに合わせて納骨式を行うのが一般的です。 また、プロテスタントでは一ヶ月後に行われる昇天記念日に納骨式が行われます。 この日に納骨を行わない場合でも遅くとも死後一年以内に納骨をします。 |
|
スポンサードリンク
| 神道「納骨式の流れ」 | |
|---|---|
| 式次第 | 神式の納骨式解説 |
神道の場合には、納骨式という呼び方ではなく納骨祭という呼び名も使われます。また墓前で行う儀式を墓前祭と言います。 |
|
| [納骨式・納骨祭] | |
| 納骨祭に先立ち、御霊前にて五十日祭を行います。 五十日祭では仮の御霊舎から本来の御霊舎へみたまを移します。 そのあと「奥津城」「奥都城」まで移動します。 ただし、神社によってはお墓(奥津城・奥都城)の前で五十日祭と納骨祭の両方を行うこともあります。霊前に様々なお供えものとしつらえます。 |
|
| 1.墓地への移動 | |
| 神職または神社の係の人が、墓地への移動を案内します。 | |
| 2.墓地にて神職によるお祓い | |
| 最初に墓所を浄めるためのお祓いを行います。 | |
| 3.納骨 | |
| 浄められた墓所にお骨を納めます。 | |
| 4.納骨の祭詞 | |
神職が祝詞(のりと)を奏上します。 |
|
| 5.玉串奉天 | |
| 玉串奉天が行われます。 玉串奉天は神職だけによって行われる場合と、神職に続き遺族も玉串奉天を行う場合とがあります。神社によって異なります。 |
|
| 6.直会 | |
| 儀式が終わり、神様にお供えしたものを下げたりお神酒を頂いたりします。 | |
| 上記のように神道では五十日祭に合わせて納骨祭を行うのが一般的です。 この日に納骨を行わない場合でも遅くとも死後一年以内に納骨をします。 |
|
スポンサードリンク
4.納骨式の服装
下記に納骨式の服装を解説します。
| 納骨式の服装 | |
|---|---|
| 納骨式を行う時期によって服装が異なります。 | |
| [忌明けの頃に行う納骨式] 仏教/四十九日の頃、 神道/五十日祭の頃、 キリスト教/1ヶ月後の追悼ミサ(カトリック)、 昇天記念日(プロテスタント)の頃に納骨を行う場合 |
|
| 納骨式はこの忌明けの頃に合わせて行うのが一般的です。 | |
| 男性の服装(男) | |
| ・施主、親族だけでなく、参列者も四十九日の忌明けまでは礼服(喪服)の場合が多いようです。 男性は、ブラックスーツ、黒ネクタイ、白いワイシャツ、黒い靴下、黒い靴。 光る時計などは避けます。 ハンカチの色も白または地味な色を。 ・学生や子供の場合(男子、男の子)、制服があれば制服で出席します。制服がない場合は黒・紺・グレーのズボン+白いシャツをベースにしますが、季節に合わせて黒、紺、グレーのジャケット(上着)、ベスト、セーターなどで寒暖の調整をしてください。ソックスは黒、紺、白。靴も黒、紺、白などが望ましいでしょう。 |
|
| 女性の服装(女) | |
| ・施主、親族だけでなく、参列者も四十九日の忌明けまでは礼服(喪服)の場合が多いようです。 女性は、黒のスーツ、黒ワンピースなど。 ストッキングは黒、靴の色も黒です。光る素材の靴やサンダルは黒色でもNGです。 光る時計やアクセサリーは避けます。パールは着用可。バッグは黒。ハンカチの色も白、黒または地味な色のものを。 ・学生や子供の場合(女子、女の子)、制服があれば制服で出席します。制服がない場合は黒・紺・グレーのズボン・スカート+白いシャツ・ブラウスをベースにしますが、季節に合わせて黒、紺、グレーのジャケット、ボレロ、ベスト、セーター、チュニックなどで寒暖の調整をしてください。タイツ・ソックスは黒、紺、白。靴も黒、紺、白などが望ましいでしょう。 ・親族の女性で、お手伝いをするためにエプロンを着用する場合には、黒、白または地味な色のものを。 |
|
| 上記以後の時期に納骨を行う場合 |
| ・忌明けの時期に納骨を行わない場合でも、死後1年以内に行うのが一般的です。 ・遺族の場合には、一周忌の法要に参列する際も略式喪服の場合が多いのですが、一般参列者が同席する場合には、一周忌以降の年忌法要以降であれば地味な平服で参列することもあります。 |
スポンサードリンク
5.納骨式の香典の表書き
納骨式に持参する香典の表書きを解説します。
宗教によって異なります。
| 宗教別の納骨式の香典の表書き | |||
|---|---|---|---|
| 表書き | |||
| 仏教 | |||
納骨式が四十九日の忌明けの法要と同じ日であれば参列者は四十九日の法要の際に香典を出します。この場合は表書きは「御霊前」。 但し、浄土真宗の場合は通夜葬儀から「御仏前」となります。 |
|||
| キリスト教 | |||
御玉串料、御神前料、御神饌料。 |
|||
| 神道 | |||
御花料。 「御供物料」という表書きは宗派を問わず使えます。 蓮の絵がついたのし袋は使えません。 白い封筒に入れます。 |
|||
| 金額の目安 | |||
法要のあとで会食がある場合にはその分を考慮した金額を包みます。 |
|||