
1.ご祝儀袋の用途と種類
結婚祝いや出産祝いなど、お祝い金を包む袋をご祝儀袋と言います。
ご祝儀袋は、「お祝い用のし袋」「お祝いのし袋」などと呼ばれることもあります。
御祝儀袋(お祝い用のし袋)は、大きく分けると以下の2つの種類に分かれます。
代表的なものは、赤白のヒモが結ばれているか、もしくは印刷されています。このヒモの部分を水引きと言います。
| 祝儀袋の用途と種類 | |||
A.蝶結び |
B1.結び切り |
B2.あわじ結び |
|
 |
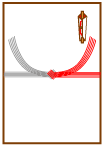 |
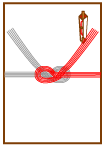 |
|
| 主な用途/結婚以外のお祝い・お礼全般 | 主な用途/ 結婚式関係 |
||
| 蝶結びは、簡単に水引きを結んだりほどいたりすることができるため、出産祝いや長寿祝いなど、人生に繰り返し何度もあると嬉しいお祝いごとに使います。 | 結び切りは、水引きを固く結んであり、解くのが難しいため、結婚祝いのように人生に一度きりにしたいお祝いに使います。 あわじ結びは結び切りの一種で、あわび結びとも言います。 |
||
| (1)結び切りのご祝儀袋 | ||||
|
||||
| No. | 用途 |
解説 |
||
| 1 | 結納金・結納飾り | 結婚に関するお祝いは一度だけで良いもの。むしろ何度もあっては困りますよね。 結婚式・婚儀に関するお祝い、お礼、お返しはすべて結び切りのご祝儀袋となります。 |
||
| 2 | 婚約祝い | |||
| 3 | 結婚祝い・結婚式お祝い | |||
| 4 | 結婚式の引出物 | |||
| 5 | 結婚祝いのお返し | |||
| 6 | 結婚に関するお礼 | |||
| 7 | 御見舞 | 病気や怪我を繰り返さないようにという願いから結び切りを用います(弔事用は亡くなった場合に使うものなのでうっかり使わないよう注意して下さい。 御見舞の際に、どうしても赤白の水引きを使うのは違和感があるという場合には、白封筒を使うと良いでしょう。 |
||
| 8 | 快気祝い | |||
| ※御祝儀袋の水引きについての詳しい解説は「祝儀袋のマナー」へ>>> | ||||
スポンサードリンク
| (2)蝶結びのご祝儀袋 | |||||
その他に、 一般的なお祝いやお礼にも用います。 |
|||||
| N0. | 用途 |
解説 |
|||
| 1 | 子供の誕生のお祝い | 出産祝い | 子供の誕生のお祝いは何度でもお祝いしたいものです。 | ||
| 2 | 出産祝いのお返し | ||||
| 3 | 子供の成長のお祝い | 子供のお祝い(お宮参り、七五三など) | 子供の成長のお祝いは何度でもお祝いしたいものです。 | ||
| 4 | 入園祝い、入学祝い、卒業祝い | ||||
| 5 | 合格祝い、就職祝い | ||||
| 6 | 長寿のお祝い | 長寿祝い(還暦祝、古稀祝、喜寿祝ほか)※長寿祝いへ>> | 長寿のお祝いは何度でもお祝いしたいものです。 | ||
| 7 | 長寿の内祝い、長寿祝いのお返し | ||||
| 8 | 一般的なお祝い | 優勝祝、受賞祝、定年退職祝、当選祝、引越祝、栄転祝、昇進祝、新築祝 | 一般的なお祝いは繰り返しお祝いしたいものです。 | ||
| 9 | お礼 | 婚礼以外の御礼全般やお返しの内祝関係など。 | おつき合いに欠かせないお礼やご挨拶は何度も使います。 | ||
| 10 | ご挨拶 | お中元、お歳暮、暑中見舞い、残暑見舞い、お年賀など | |||
| 11 | 神社や神職へのお礼 | 祈祷(きとう)や祝詞(のりと)、婚礼以外のお祝に関するの神社や神職へのお礼全般 。御神饌料、初穂料、玉串料など。 | |||
| 12 | その他 | お年玉、心づけ・チップ、お餞別、おはなむけ、御車代。 神事や祈祷の際の御酒肴料、お祭りの時の御祝儀など |
お祝いやお付き合い関係の用途です。 | ||
| ※御祝儀袋の水引きについての詳しい解説は「祝儀袋のマナー」へ>>> | |||||
| ※一般的なお祝いやお礼、蝶結びの祝儀袋を使う場合の書き方については別ページ「祝儀袋の書き方」へ>>> | |||||
スポンサードリンク
| 2.ご祝儀袋の書き方と表書き |
| それでは早速、用途別の表書きと書き方を解説します。 |
| (1)書き方のマナー |
| a. 毛筆で書く |
| ボールペンや、サインペンで表書きを書くのはNG。毛筆で書くのが正式なマナーです。 どうしても苦手な場合には、(略式になりますが)筆ペンでも良いでしょう。 |
| b. 濃い墨で書く |
| 慶事(お祝い事)、お礼、御祝儀などは、濃い墨で書きます。 (※参考情報/弔事の場合には薄墨で書きます) |
| (2)目的別・用途別の表書きの書き方 | |
| [結び切りの御祝儀袋を使うグループ] | |
| a. 結納金・結納飾り | |
| 結納飾りの中の結納品についてはそれぞれの縁起の良い品目ごとに熨斗紙がついていますので、ここでは略式結納の場合に使いそうな表書きをご紹介します。 | |
| 用途 | 表書きの書き方 |
| 結納金 男性から女性へ | |||||
御帯料、御帯地料、小袖料(関西) [下段] 新郎本人のフルネームまたは姓を書く |
|||||
| 結納返し 女性から男性へ | |||||
| [表書き] 御袴料、御袴地料 [下段] 新婦本人のフルネームまたは姓を書く |
|||||
| b. 結婚式・結婚祝い・結婚祝のお返し・結婚式に関するお礼 | |
| 結婚式に関わるものは、すべて結び切りの祝儀袋を使います。 | |
| 用途 | 表書きの書き方 |
| 結婚祝い 親族、友人、来賓から新郎新婦へ | |||||||
寿、祝御結婚、御結婚御祝、御祝、御慶など [下段] 本人のフルネームまたは姓を書く |
|||||||
| 結婚祝のお返し 披露宴に招待できなかった人へ | |||||||
[のし紙の表書き] 内祝、寿 [下段] 新郎新婦のフルネームまたは名前を並べて書く。もし結婚後に贈るなら、二人とも姓が同じなので夫婦連名の書き方にて(右の見本画像を参照) |
|||||||
| 引出物 披露宴に招待した相手に | |||||||
[のし紙の表書き] 寿 [下段] 新郎新婦の家から出す引出物は両家の姓を書き、新郎新婦本人から出すものは、新郎新婦の氏名もしくは新郎新婦の名前のみを書きます。 例えば引出物は両家の姓、引菓子は新郎新婦の氏名などとなります。 |
|||||||
| 用途 | 表書き |
| お礼
仲人媒酌人や、結婚式の司会、受付係を頼んだ相手に 着付係、世話係などにも |
|
| [表書き] 寿、御礼 [下段] 原則として、両家で依頼した媒酌人や司会者などは両家の姓を書き、新郎新婦のそれぞれが依頼した相手には、頼んだ新郎の氏名もしくは新婦の氏名。 |
|
| お車代 結婚式の来賓、主賓に | |
| [表書き] 御車代 [下段] 原則として、両家で依頼し主賓、来賓あてのものは両家の姓を書き、新郎新婦のそれぞれが依頼した相手には、頼んだ新郎の氏名もしくは新婦の氏名。 |
|
スポンサードリンク
| [結び切りの御祝儀袋を使うグループ](つづき) | |
| c. 御見舞い | |
|
病気や怪我に関することは、お祝いと言うよりも二度と繰り返さないようにという願いから結び切りののし袋を使います。
どうしても赤白の水引きに抵抗があるという場合には白封筒で。
なお、病気や怪我のお見舞ではない場合(楽屋見舞いや陣中見舞いなど)は結び切りではなく蝶結びのものを使います。 また、地震見舞い、水害見舞いなどの災害見舞いについては白封筒を用います。 |
|
| 用途 | 表書き |
| 病気や怪我のお見舞い 怪我や病気などで入院している相手など |
[表書き] 御見舞、祈御全快、お見舞 [下段] 姓またはフルネームなど |
| d. 快気祝い | |
| 病気や怪我に関することは、お祝いと言うよりも二度と繰り返さないようにという願いから結び切りの御祝儀袋、のし袋を使います。 | |
| 用途 | 表書き |
| 快気祝い 怪我や病気が回復したときや、お見舞のお礼など |
[表書き] 快気祝、快気内祝 [下段] 本人の姓を書く |
[蝶結びの御祝儀袋を使うグループ] |
| ※蝶結びの祝儀袋を使う場合の書き方については別ページ「祝儀袋の書き方2」へ>>> |
| 3. 御祝儀袋の下段の書き方 (個人、夫婦、連名、ビジネスなど) |
| ご祝儀袋の下の段について、代表的な書き方を下記にご紹介します。 |
| ご祝儀袋の差出人の書き方 | |
| 姓またはフルネームを書くとき | 夫婦連名のとき |
フルネームの場合も同様です。 |
夫の名前の左側に妻の名前をやや控えめに書きます。 |
| ご祝儀袋の下の段の書き方 | |
| 連名の場合(3名) | |
……中心、左、右に、対象になるようにバランスよく配置します。 |
……中心に最も格上もしくは年長者の氏名を書きます。二番目の人はその左に、三番目の人は最も左に書きます(左の見本では甲、乙、丙の順) |
| 連名の場合(4名以上) | |
受け取り手がお礼状を出せるように、メンバーの住所氏名を書いたリストを中に入れます(半紙や奉書紙に毛筆で書くのが正式ですが、便箋にペン書きの略式でも可)。全員が同額であれ金額の内訳は書きません。 |
|
| ご祝儀袋の下段の書き方(ビジネスの場合) |
| ビジネスの場合 |
会社名や肩書を書き添える場合には、氏名が中心に来るように書き、社名は右側に小さく書き添えます。 長くなる場合には、株式会社は(株)などと省略しても構いません。 |
| 連名の場合(4名以上) |
相手先がお礼状を出せるように、メンバーの住所氏名を書いたリストを中に入れます(半紙や奉書紙に毛筆で書くのが正式ですが、便箋にペン書きの略式でも可)。 メンバーリストは、必ず目上の人の氏名から順に書きます。 なお、 毎日会う間柄の場合には住所は省略されることもあります。 また、 全員が同額であれ金額の内訳は書きません。 ※3名までの連名の場合には、個人の場合と同様に上司や目上の人があれば中心から左へと順番に書いていきます。対等な関係の3名の場合には、センター、右、左、というように左右対称になります。 |
スポンサードリンク
| 4.中袋の包み方 |
| ご祝儀袋の中袋の包み方について説明します。 金額の書き方は別ページ「中袋の書き方」へ>>> |
| お札の表と裏 (お札はどっちがおもて?) |
祝儀袋に入れる時にお札の表と裏が必要になってくるので |
| 中包みのお金の包み方 |
まず最初にお金を置く位置を決めるためのガイドラインを作ります。 右の見本のように下から上に折り目をつけます。 |
お札が二枚以上の場合には、お札の向きを揃えます。結婚のお祝いの時にはお札は新札を用いるのが慣例となっています。 また最終的に表側(人物の顔のある側)がのし袋の表側に来るように包むのが正式とされています |
|
|
これにより、下の⑤ではこれまで下を向いていた面が出たことになります。 |
|
| ⑥上の⑤を裏返すと中包みが完成! 人物のある側がおもてに出ることになります。 |
|
|
※但し左下が開いた形は弔事用なのでNGです |
それぞれの袋や包みの中身は左のようになります。 ※中包みを上包みで包む時の包み方はこちら「中包みの書き方」へ>>> |
|
スポンサードリンク
| 5. 結婚式・結婚祝の金額 |
| 結婚式のお祝い金の金額は相手とのお付き合いの程度や、贈り主の年齢などによって異なります。 結婚の御祝儀の場合、縁起を担いで「2つに割ることができる数字=偶数」はあまり好まれないため、10,000円、30,000円、50,000円などの金額が用いられます。但し2万円は「対」を表わすためOKとされます。なお、10万円、20万円などの金額はOK。 下記は参考例です。もちろんもっと沢山包んでも構いません。 |
| 結婚祝い・結婚式のご祝儀の金額 (一般的な金額) | |
| 招待客(あなたと新郎新婦との関係は?) | 御祝儀の金額 |
| 新郎新婦の兄弟姉妹 | 50,000〜100,000円 |
| 新郎新婦の兄弟姉妹(夫婦) | 100,000円〜 |
| 新郎新婦の親族 | 30,000円〜 |
| 親族(夫婦) | 50,000〜100,000円 |
| 友人 | 30,000円 |
| 同僚 | 30,000円 |
| 部下 | 20,000円(20代)〜30,000円 |
| 上司 | 30,000円、50,000円など |
| 上司(夫婦) | 70,000円、100,000円など |
| 招待されていない人 | 御祝儀の金額 |
| 友人・同僚 | 3,000〜20,000円 |