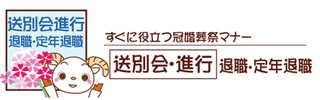
| ………もくじ……… |
|---|
| ▼1.定年退職の送別会の進行 |
| 1-1.事前に準備すること、1-2.当日の流れほか |
| ▼2.退職の送別会の進行 |
| 2-1.事前に準備すること、2-2.当日の流れほか |
| [関連ページ] |
| ・送別会の進行 台本・シナリオ・進行表> |
| ・送別会の挨拶(送る側)> |
| ・送別会の挨拶(送られる側)> |
| ・退職メッセージ> |
| ・門出を祝うメッセージ> |
| ・はなむけの言葉 退職(1)> |
| ・はなむけの言葉 退職(2)文例集> |
| ・はなむけの言葉 転職> |
| ・はなむけの言葉 転勤> |
| ・はなむけの言葉 異動> |
| ・餞別(せんべつ)> |
| ・はなむけの言葉 贈る言葉・名言(退職, 異動, 結婚, 卒業, 英語)> |
| ・退職者・定年退職者に贈る言葉 名言> |
| ・送別メッセージ・メッセージカード> |
| ・送別メッセージ 上司> |
| 1.定年退職の送別会の進行 |
| 会社・職場などで、退職や、定年退職をする人の送別会の進行、台本、プログラム(式次第、流れ)を紹介します。 |
| 定年退職の送別会の進行 | |
| 1-1.事前に準備しておくこと | |
| 1)幹事を決める | |
| ・幹事、司会、会計係などを決めます。幹事がすべて兼ねることもあります。 | |
| 2)定年退職する人のプロフィールと足跡等をチェックしておく | |
・定年退職する人の所属、氏名、入社年度を確認しておきます。 |
|
| 3)送別会の日程を決める | |
・定年退職者の都合と、出席者の中で最も上の立場の人の都合を確認し、相談の上で送別会の日程を決めます。 |
|
| 4)出席人数を確認し、会場や料理、飲み物の手配をする | |
・送別会のおよその出席人数は何名か、会場は貸し切りか等を確認しておきます。 |
|
| 5)メールや掲示などで、送別会の案内をする | |
・メールや掲示などで送別会の案内をします。 ・定年退職者本人には異なる案内文で招待のニュアンスのあるメールを送るか、書面で案内をします。 |
|
| 6)記念品を渡すかどうか決める | |
・会社によっては定年退職者に会社として退職記念品を渡すことがあります。人事や総務などが担当となりますので、幹事は事前に確認をしておきます。 |
|
7)につづく |
|
スポンサードリンク
| 定年退職の送別会の進行(つづき) | |
| 1-1.事前に準備しておくこと(つづき) | |
| 7)花束を渡すかどうか決める | |
| ・花束は退職の送別会で渡す贈り物としては最も一般的なものです。当日渡すかどうかを決めておきます。 ▼花束を渡す係を決め、依頼する。 ・どんな人に依頼?…例えば退職する人と同じ部署の女性、新人女性など。女性に依頼するのが一般的です。 |
|
| 8)当日の進行を考えておく | |
| ・当日の進行、プログラム、流れを考えておきます。 | |
| 9)万歳三唱をするかどうか決める | |
| ・万歳三唱は激励の意味で行うものですが、会場によってはできないものです。行うかどうかを決めておきます。 ▼万歳の発声をする係を決め、依頼する。 ・どんな人に依頼?…例えば当日の出席者で3番めの地位にいる人、退職者が以前にいた部署の上司など。 |
|
| 9)挨拶や乾杯の音頭を依頼しておく | |
| ▼1.定年退職者のプロフィールや足跡、功績を紹介する人は誰にするのかを決めて依頼します。 ・どんな人に依頼?…例えば、定年退職する人の直属の上司、人事担当、総務担当に依頼するか、幹事、司会者などが行うのが一般的です。 ▼2.乾杯の音頭は誰に依頼するのかを決めて依頼します。 ・どんな人に依頼?…例えば、出席者の中で役職の序列が上から2番めの位置にいる人など。あるいは、上記▼1で、プロフィール紹介を幹事や司会者が行った場合には直属の上司がおこなうこともあります。 ▼3.定年退職者に送る言葉、はなむけの挨拶を誰に依頼するのかを決めて依頼します。1〜2名 ・どんな人に依頼?…例えば、出席者の中で役職の序列が一番上の人が一般的。 更に依頼する場合には退職する人と最も交流が深かった人や、退職者に最もお世話になった人、あるいは業務上でその仕事を継ぐ後継者となる人など。 |
|
| 10)定年退職する本人にも一言挨拶を依頼しておく | |
| ・主役となる定年退職者自身にも、当日いきなり挨拶をと言われて困惑させたり恥をかかせることの無いよう、あらかじめ一言挨拶を依頼しておきます。 |
|
スポンサードリンク
| 定年退職の送別会の進行(つづき) |
| 1-2.当日の流れ |
| (1)開会宣言 |
| ・送別会の開始を宣言する。送られる人の名前を読み上げ、開始を知らせる。 「ただいまより◯◯さんの退職送別会を始めます」 「ただいまより◯◯年度退職者送別会を始めます」など。 ・出席者は雑談をやめて司会者に注目する |
| (2)定年退職者の紹介 |
| 退職する人のプロフィールを簡単に紹介してもらいます。 幹事や司会者が退職者の足跡、功績を紹介することもあります。 |
| (3)乾杯 |
| 乾杯の音頭のあと、乾杯となります。 |
| (4)食事・歓談 |
| しばらくは食事や歓談となります。主役が各テーブルを回って挨拶を交わす時間となります。ビールやお酒を注いだりすることもあります。 |
| (5)送別の言葉、はなむけの言葉 |
| ・送る人のスピーチ。時間が許せば2人程度まで ※参考ページ…送別会の挨拶(送る側)>>> |
| (6)花束贈呈・記念品贈呈(※ 会社や職場によっては(6)は省略されます) |
| (7)定年退職者の挨拶 |
| 定年退職者本人、送られる人が挨拶をする。 ※参考ページ…送別会の挨拶(送られる側)>>> |
| (8)万歳三唱など(※ 会社や職場によっては(8)は省略されます) |
| (9)閉会宣言 |
| ・送別会の閉会を宣言する。 ・二次会がある場合にはその案内をする。 |
| ★ 参考ページ…送別会の進行、台本、シナリオ>>> |
スポンサードリンク
| 2.退職の送別会の進行 |
| 会社・職場などで、結婚、転職、独立、家族の事情、家業の継承、健康上の理由、その他の理由で退職をする人の送別会の進行、台本、プログラム(式次第、流れ)を紹介します。 |
| 退職の送別会の進行 | |
| 2-1.事前に準備しておくこと | |
| 1)幹事を決める | |
| ・幹事、司会、会計係などを決めます。幹事がすべて兼ねることもあります。 | |
| 2)退職する人のプロフィールと退職理由をチェックしておく | |
・退職する人の所属、氏名を確認しておきます。 |
|
| 3)退職の送別会の日程を決める | |
・退職者の都合と、出席者の中で最も上の立場の人の都合を確認し、相談の上で送別会の日程を決めます。 |
|
| 4)出席人数を確認し、会場や料理、飲み物の手配をする | |
・送別会のおよその出席人数は何名か、会場は貸し切りか等を確認しておきます。 |
|
| 5)メールや掲示などで、送別会の案内をする | |
・メールや掲示などで送別会の案内をします。 ・退職者本人には異なる案内文で招待のニュアンスのあるメールを送るか、書面で案内をします。 |
|
| 6)花束を渡すかどうか決める | |
| ・花束は退職の送別会で渡す贈り物としては最も一般的なものです。当日渡すかどうかを決めておきます。 ▼花束を渡す係を決め、依頼する。 ・どんな人に依頼?…例えば退職する人と同じ部署の女性、新人女性など。女性に依頼するのが一般的です。 |
|
7)につづく |
|
スポンサードリンク
| 退職の送別会の進行(つづき) | |
| 2-1.事前に準備しておくこと(つづき) | |
| 7)当日の進行を考えておく | |
| ・当日の進行、プログラム、流れを考えておきます。 | |
| 8)万歳三唱をするかどうか決める | |
| ・万歳三唱は激励の意味で行うものですが、退職の理由によっては万歳にふさわしくないものもあります。起業・独立・留学のための退職などの場合にはふさわしいと言えます。 また、大勢で声を上げるため会場によってはできないこともあり、万歳三唱を行うかどうかを決めておきましょう。 ▼万歳の発声をする係を決め、依頼する。 ・どんな人に依頼?…例えば当日の出席者で3番めの地位にいる人、退職者が以前にいた部署の上司など。 |
|
| 9)挨拶や乾杯の音頭を依頼しておく | |
| ▼1.退職者のプロフィールや足跡、功績を誰に紹介してもらうのかを決め、依頼しておきます。 ・どんな人に依頼?…例えば、退職する人の直属の上司、人事担当、総務担当に依頼するか、幹事、司会者などが行うのが一般的です。 ▼2.乾杯の音頭は誰に依頼するのかを決めて依頼します。 ・どんな人に依頼?…例えば、出席者の中で役職の序列が上から2番めの位置にいる人など。あるいは、上記▼1で、プロフィール紹介を幹事や司会者が行った場合には直属の上司がおこなうこともあります。 ▼3.退職者に送る言葉、はなむけの挨拶、お礼の言葉を誰に依頼するのかを決めて依頼します。1〜2名 ・どんな人に依頼?…例えば、出席者の中で役職の序列が一番上の人が一般的。 更に依頼する場合には退職する人と最も交流が深かった人や、退職者に最もお世話になった人、あるいは業務上でその仕事を継ぐ後継者となる人など。 |
|
| 10)退職する本人にも一言挨拶を依頼しておく | |
| ・主役となる退職者自身にも、当日いきなり挨拶をと言われて困惑させたり恥をかかせることの無いよう、あらかじめ一言挨拶を依頼しておきます。 |
|
スポンサードリンク
| 退職の送別会の進行(つづき) |
| ここでは少人数の場合の退職送別会の進行を紹介します。人数が多い場合にはこちらに準じます>>> |
| 2-2.当日の流れ |
| (1)開会宣言 |
| ・送別会の開始を宣言する ・送られる人の名前を読み上げ、開始を知らせる 。 ・出席者は雑談をやめて司会者に注目する |
| (2)乾杯 |
| (3)食事+送る言葉 |
| 料理が一度に出るわけではないので、内輪の送別会では冒頭の時間を少しだけ挨拶タイム(お礼の言葉、激励メッセージの時間)とする。 1(もしくは2人くらい)スピーチをしたところで、一旦食事タイムとする。しばらくは食事や歓談となる。主役をネタにしながら盛り上がる時間帯。 ネガティブな話題は避けるようにしたい。 |
| (4)送別の言葉、はなむけの言葉、御礼の言葉 |
・送る人のスピーチ。送る側の中で最も上の立場にある人がスピーチをする。 |
| (5)退職者挨拶・転勤者挨拶 |
| ・退職者本人、送られる人が挨拶をする。 |
| (6)花束贈呈・記念品贈呈(※ 会社や職場によっては(6)は省略されます) |
| (7)万歳三唱など(※ 会社や職場によっては(8)は省略されます) |
| (8)閉会宣言 |
| ・送別会の閉会を宣言する。 ・終わると言わずに「お開き」の言葉を使うと良い ・二次会がある場合にはその案内をする。 |
| ★ 参考ページ…送別会の進行、台本、シナリオ>>> |