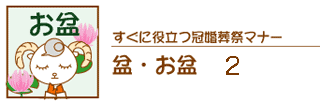
| ………このページの内容……… |
|---|
| ▼1. 盆・お盆とは 前のページへ |
| ▼2. お盆の期間・時期 前のページへ |
| ・盆の入り、盆の明け |
| ▼3. お盆のさまざまなしきたり 前のページへ |
| ・お盆の飾り(精霊棚、盆提灯)、迎え火と送り火、盆供 |
| ▼4. お盆の迎え火・送り火 |
| ・迎え火を焚く時間、やりかた、送り火を焚く時間、やりかた |
| ▼5. お墓参り |
| ▼6. お盆の服装 |
| ▽ 参考情報 卒塔婆と経木塔婆について |
| … 関連ページ … |
| ※ 別ページ…初盆・新盆 お供え>> |
| ※ 別ページ…初盆を家族だけでする場合 |
| お盆の迎え火・送り火 | |||
| ※お盆のしきたりは、地方によっても宗派によっても異なります。 | |||
| 項目 | 解説 | 補足説明 | |
| 迎え火 | ||
| ●迎え火はいつ焚くの? | ||
| ●8月13日(または7月13日)の夕方に | ●盆の入り・お盆の入りの日に、火を焚いてお迎えします。祖先の霊が迷わずにこの火を目印にして戻って来てくれるようにというものです。 | |
| ●迎え火の材料は? | ||
| ●おがら、麦藁など ※おがら=皮を剥いだ麻の茎。「苧殼」 |
●市販されているものは、おがらや薪などと素焼きの皿、焙烙(=ほうろく、ほうらく。素焼きの平たい土鍋)がセットになっているもの等があります。セット品は仏具店や、一部のホームセンターなどで扱っています。おがらは花屋などでも販売されるようです。 |
|
| ●迎え火のやりかた、 ●迎え火のしかた | ||
| ●もともとは迎え火の火はお墓で灯していました。13日にお墓参りをし、お墓の前で迎え火の火を灯して提灯に入れて家まで持って帰ってきます。その火を仏壇の蝋燭(ろうそく)に移していました。 ●現代ではお墓が遠いため提灯に入れて迎え火を連れて来ることが難しい場合も多くなっています。そうした場合には、13日の夕方に、門口や玄関前などの危なくない場所で迎え火を焚きます。その際に、精霊馬があれば近くに置きます。 仏壇の蝋燭から火種をおがらなどに移す方もいらっしゃるようです。 |
●迎え火は、地方により、また宗派によってさまざまなやり方があります。 焙烙の上でおがらを燃やす迎え火の他に、たき火のように燃やすものや、篝火(かがり火)のように燃やすものもあります。 ●初盆・新盆の場合には、霊が迷わずに戻って来られるようにと白提灯も灯す風習があります。特にマンションなどの場合、迎え火を焚くのが難しいため、迎え火の代わりに白提灯を用いることも多いようです。 安全上の理由から提灯に入れるロウソクの代わりに電池灯を用いることもあります。 白提灯については初盆・新盆のページで詳しく説明しています>>> |
|
スポンサードリンク |
| お盆の迎え火・送り火 (つづき) | ||
| 項目 | 解説 | 補足説明 |
| 送り火 | ||
| ●送り火はいつ焚くの? | ||
| ●8月16日(または7月16日)に。但し、地域によっては15日に行います。 火を焚く時間は、午後〜、夕方〜、夜になってからとさまざまです。 |
●お盆明けの日に、火を焚いて先祖の霊をお送りします。帰り道に迷わずあの世にもどれるようにというものです。 ●例えば京都五山の送り火は、文字どおり送り火のひとつで8月16日に行われます。午後8時頃点火されます。 |
|
| ●送り火のやりかた ●送り火のしかた |
||
| ●門口や玄関前などの危なくない場所で送り火を焚きます。 仏壇の蝋燭から火種をおがらなどに移す方もいらっしゃるようです。 やり方、材料は迎え火と同じです。 |
●役目を終えた白提灯も送り火で燃やします。盆棚も燃やす地域があります。 マンションなどでは送り火で白提灯を燃やすのが難しくなっていますが、菩提寺に持参して供養してもらうこともできます。 |
|
| お墓参りのしかた(仏教の場合) | |
| A 準備するもの | |
| 1.掃除用具 | |
| お墓、墓石および周辺を掃除するための道具です。 墓地や霊園に備え付けられている場合もあります。 |
|
| 軍手 | |
| ・お墓の周辺の雑草を取る時に使います。 ・墓地の場所によっては、草刈りガマや、スコップが必要なこともあります。 |
|
| バケツ | |
| ・雑巾やたわしなどを洗浄する際に用います。 | |
| 雑巾 | |
| ・墓石を拭き清めます。 | |
| たわし (スポンジ、歯ブラシ) | |
| ・墓石についたコケなどを落とします。金属製たわしはNGです。 ・ 墓石の 材質によってはタワシを使うと表面を傷つけてしまうこともあり、スポンジや歯ブラシの方が適していることもあります。 |
|
| ほうき | |
| ・お墓の周辺を掃き清めます | |
| ちりとり | |
| ・ホウキで掃いた落ち葉、ゴミなどを集めるのに用います | |
| ゴミ袋 | |
| ・ゴミや、引き抜いた雑草を持ち帰ります。 ・墓地や霊園によってはゴミ捨ての場所が設けられているところもあります。ゴミ捨ての場所がない墓地や墓園でお花を取り替えた場合には、古いお花を持ち帰ることもあります。 |
|
スポンサードリンク
| 2.お参りや供養の際の持ち物 | |
| 供養のための道具です。 手桶などは、墓地や霊園で借りられる場合もあります。 |
|
| 白提灯・盆提灯 | |
| ・初盆の場合、お墓の前でロウソクに火を灯し、自宅まで運びます。 (お墓が遠くにある場合には行われません。また、地域や宗派によってしきたりが異なります) |
|
| 手桶 | |
| ・墓石にかける水を入れて運びます。 | |
| 柄杓 (ひしゃく) | |
| ・手桶の水を墓石にかけるときに用います。 | |
| 線香 | |
| ・墓前に供えます。 | |
| ロウソク | |
| ・ろうそくはお線香の点火に使います。また、盆提灯に入れて迎え火を持ち帰る時にも用いることがあります。 | |
| マッチなど | |
| ・ろうそくの点火に使います。 | |
| お供え物 | |
| ・お花、お水、お菓子など。 お花の茎を切るハサミや、お供えを置くための半紙なども持参すると良いでしょう。 |
|
| 3.お墓参りの服装 | |
| 初盆・新盆などの法事法要に合わせてお墓参りをする場合には喪服(礼服や準礼服など)となりますが、法事法要とは関係なくご先祖に会いに行くお墓参りには、決まった服装はありません。 但し、他のお墓にもお参りに来られている遺族の方がいらっしゃいますので、極端に華美な服装や香りの強い香水などは避けるのがマナーです。 ※宗教・宗派によっても異なりますので、ご自身の宗教に従って下さい。 |
スポンサードリンク
| お墓参りのしかた(仏教の場合)つづき | |
| B お墓参りのマナーや作法(仏教の場合) | |
| 1.墓地に入る前に、ご本堂の前で一礼 | |
| お寺の墓地の場合には、お参りの前に本堂、本尊にお参りします。 | |
| 2.手を洗い浄めます。 | |
| 3.手桶に水を汲み、墓地に向かいます。 | |
| 手桶とひしゃくを借りられる墓地もあります。 | |
| 4.自分の家のお墓の前についたらまずは一礼します。 | |
| 両手を合わせて合掌します。 |
| 5.お墓と、お墓の周りの掃除をします。 | |
| ・周りの雑草や落ち葉などを取り、墓石についた汚れをおとします。 墓地ごとにルールがありますので、決められたルールにしたがって清掃をしましょう。 |
|
| お墓のまわり | |
| ・花立て、線香立て、線香皿、水鉢、燭台などもきれいにします。枯れた花が残っていれば取り除き、花立てをきれいにします。 ・周辺をホウキで掃き清め、雑草を取ります。 |
|
| 墓石 | |
| ・墓石にきれいなお水をかけて清めます。 ・スポンジや柔らかいたわしを用いて汚れを落とします。 細かいところは、歯ブラシを使うと良いでしょう。力を入れると石を痛めますのでやさしく汚れを落とします。 |
|
| 6.お墓がきれいになったらお線香を供え、お花やお菓子などのお供えをし、拝礼をします。 | |
| ・お花、お水、お菓子などをお供えします。 ※卒塔婆については、こちらをご参照下さい>>> |
|
| お花 | |
| ・お花はお供えしたまま帰ることになります。あとで倒れないようにハサミで短かめに切ってお供えします。 | |
| お水 | |
| ・墓石のてっぺんからひしゃくで手桶のきれいなお水をかけて清めます。 ・お水を御供えする器(水鉢)があればきれいなお水を入れます。 |
|
| お線香 | |
| ・燭台があれば、ロウソクを立て、ロウソクにマッチなどで点火します。 次に、ろうそくから線香の束に火をつけます。炎(ほのお)が出てしまったら口で吹き消すのではなく、手であおいで炎だけを消し、お線香の先端だけが赤く灯った状態にします。 ・線香立てにお線香をお供えします。 (立ててお供えする、寝かしてお供えするなど、宗教によって異なるようです。また、線香の本数も1本を立てる、2本を立てる、1本を折って横に寝かすなどの宗派があります。) |
|
| お供え物 | |
| ・半紙または持参した器などの上にお供えをし、お参りが終わったら持ち帰るようにします。 | |
| 合掌・拝礼 | |
| ・両手を合わせ、先祖や故人の冥福を祈ります。 ・近況の報告をしたりします。 ・お経を唱えることができれば、お経を唱えても良いでしょう。 ・特にこだわる必要はありませんが、もし家族で参拝する時に、拝礼の順番を気にする場合には、血縁の濃い順から参拝しましょう。 ・墓石がたくさんある場合には、古い祖先のお墓にもお参りします。 |
|
| [墓前回向・墓前読経・盆会墓前読経] ・事前にお寺に申し込みをしておけば、墓前読経をしていただくこともできます。 |
|
| 迎え火の持ち帰り | |
| ・迎え火を持ち帰る場合には、墓前のろうそくで提灯のロウソクに火を移し、消えないように持ち帰ります。 | |
スポンサードリンク
| お盆の服装 |
| [施主および遺族] ◎初盆・新盆の法要には喪服を着用する場合が多いようです。 男性はブラックスーツに黒のネクタイ、靴下も靴も黒です。 女性は黒無地のワンピースやアンサンブルにパールのネックレスなど。ストッキング、靴も黒です。 ◎ただし、親族のみで初盆を行う場合、および2年目以降には、喪服でなくても地味な服装であれば良いでしょう。 お墓参りをする場合には派手な帽子や派手な日傘はタブーです。 |
| [初盆・新盆の法要に招かれた場合] ◎例えば故人の知人や友人など初盆・新盆の法要に招かれた方は、略式喪服を着用するのが正式なマナーですが、施主や遺族よりも礼服の格が上にならないように注意して下さい。 最近では暑い季節ということから地味な平服で参列することも多くなってきました(地域や宗派および故人や施主とのおつきあいの程度によります) ◎暑い季節ですので、調節ができる服装を工夫してください。ごく内輪の方のみであれば白いボタンダウンシャツに黒またはグレーのズボンなどでも良いのではないでしょうか。 ◎学生の場合は、制服が基本です。 制服がない場合および、子供の服装は、白いブラウスまたはシャツに黒、紺、グレーのズボンまたはスカートなど。 なお、お手伝いをする場合には、白、黒または地味な色調の無地のエプロンや葬式用エプロンとして販売されているものなどを持参してください。 |
| |||
スポンサードリンク