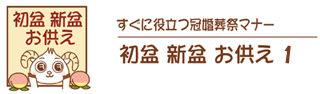
| ………このページの内容……… |
|---|
| ▼1. 初盆・新盆とは |
| ・初盆と新盆とは同じ意味。地域による違い |
| ・初盆・新盆の時期は? |
| ▼2. 初盆・新盆のお供え・お供え物 |
| 2-1)お供物・お供え・お供え物ののしの書き方 表書き |
| 2-2)初盆・新盆のお供えの飾り方 |
| ・お膳、盆飾り |
| ▼3. 初盆・新盆のお供え・お供え物・御供物として人気があるのは…次のページ |
| ▼4. お供え・お供物・御供物を送る場合…次のページ |
| ・手紙を添える場合…次のページ |
| ▼5. お返し、お礼…次のページ |
| [関連する別ページ] |
| ※ 初盆・新盆のマナー・作法・流れ>>> |
| ※ 初盆のお返し・浄土真宗の初盆>>> |
| ※ 初盆のお布施・新盆のお布施>>> |
| ※ 初盆の服装・新盆の服装>>> |
| ※ 初盆・新盆 お供え2 >> |
| ※ 初盆 家族だけでする場合>> |
| ※ 家族だけの一周忌法要>>> |
●初盆と新盆とは同じ意味。地域による違いだった!
初盆・新盆とは忌明け後に初めて迎えるお盆のことをさし、僧侶を招いて法要が行われます。
初盆と新盆とは同じ意味です。全国的には大半の地域で初盆(はつぼん)と言われていますが、関東甲信越地方のみで新盆(にいぼん、あらぼん、しんぼん)と呼ばれていたようです。
[注1]
[注1](NHKが1978年に農林水産通信員を対象にした調査による。詳細は参考ページ「NHK放送文化研究所「初盆」と「新盆」についての使い分けや決まりはある?」を参照。別ウインドウが開きます)>>>
●初盆・新盆の時期は?
初盆・新盆の時期は、新暦または旧暦の7月15日頃となります。
仏教の盂蘭盆(うらぼん)・盂蘭盆会(うらぼんえ)が元になっています。
旧暦の7月15日頃は新暦では8月15日前後にあたりますが、東京や横浜市の一部等では、新暦となった今でも7月15日頃にお盆の行事を行うため、日本全国でみると新暦の7月15日頃にお盆を行う地域と、8月15日頃にお盆を行う地域とが混在しています。
| 2-1)初盆のお供え・お供え物・お供物ののしの書き方・表書き | |||
| 一般的な仏教の各宗派(臨済宗、曹洞宗、日蓮宗、真言宗、浄土真宗など) | |||
お供えの表書き |
墨の色 |
水引の色・水引きの色 |
|
| 御供 | 濃い墨 |
|
|
| (現金を包む場合) 御供物料 |
|||
最近は初盆の法要の際にお供えをしたい場合、品物を持参したり送る代わりに「御供物料」として現金を包む人も多くなっているようです。
品物よりも現金を用意する理由としては、法要の会場によってはお供えするスペースが限られている場合があったり(お寺・自宅・斎場その他)、お供物として頂いた品物は、法事が終わると遺族や親族などで取り分けることになり好みや人数によっては遺族や親族が困るケースも想定されること、などが挙げられます。
また、お供え・お供物を用意するとしても出席者が持参する場合と送る場合があります。例えば初盆の案内状をもらっても出席できない場合には、会場と日程があらかじめわかっているため、事前に手配して送ることもあります。送る場合の注意点などは次のページの項目4.「お供え・お供物・御供物を送る場合」で解説しています。>>>
スポンサードリンク
2-2)初盆・新盆のお供えの飾り方
初盆・新盆に際し、仏壇にお菓子、果物 やお花などをお供えすることがあります。参列者(親戚・親族・友人など)から頂くお供え物だけでなく仏壇の周辺が寂しくないようにとお供えする目的で、遺族が手配することもあります。
初盆・の儀式(盂蘭盆、盂蘭盆会)の儀式のために、精霊棚をしつらえることがあります。地方や宗派によって異なり、浄土真宗では精霊棚は飾らないとされます。精霊棚については初盆の飾り付けのページへ>>>
精霊棚をしつらえる場所は仏壇の前などが一般的で、お盆の期間は仏壇から位牌を出して精霊棚に飾ります。もし精霊棚をしつらえた場合には下記のお供え物は、精霊棚の前に飾って下さい。
| 2-2)初盆・新盆のお供え、お供え物の飾り方 |
お盆には、初盆を迎える故人だけでなくご先祖様たちも帰ってきます。 |
スポンサードリンク
| 初盆のお膳(お供え膳)つづき |
お供え膳の献立 |
| お膳の向きは、遺族は自分に向けて置き、仏壇用のお膳は仏壇を向けて置きます。 (つまりお供え膳はお箸のある側が仏壇側となります) 精進料理の献立は、五色、五味、五法に則って立てられます。 五色…赤、緑、黄色、白、黒 五味…甘味、塩味、酸味、辛味、苦味 五法…煮る、焼く、蒸す、揚げる、切る(または「生」「漬ける」という言い方もあります) 宗派によっては、上記にこだわらずに故人の好きなものを用意することもあります。 お膳を置く場所はお仏壇の前ですが、もし精霊棚をしつらえた場合にはその前に置いて下さい。 |
ご飯、汁物とは別に五菜(5種類のおかず)を用意します。 一例をご紹介します。 故人がお好きだったものや、季節の旬の野菜を取り入れた献立が良いでしょう。 1. 煮物 2. 和え物 3. 煮豆 4. 漬物 5. 佃煮、海藻など |
ご飯、汁物とは別に三菜(3種類のおかず)を用意します。 一例をご紹介します。 故人がお好きだったものや、季節の旬の野菜を取り入れた献立が良いでしょう。 1. 煮物 2. 和え物 3. 漬物 など |
| ①−2. お供え・お供え物の飾り方、お供えのしかた |
果物は皮をむく…食べやすいように切る |
| お菓子は包装紙を解き、箱から出してお供えする |
| お花は水替え、水やりを欠かさないようにし、枯れた花は取り替える。 |
| ロウソクは火災の危険がないように必要な時に灯す。 (消す時は息を吹きかけて消さないように) |
| 線香はお仏壇にお参りの際に時に灯す。 (火災の危険が無いように注意する) |
| お水は水替えを欠かさないようにする。 |
| ※注意…宗派によってはお仏壇にお供えしないものもあります。各宗派のしきたりはお寺に確認してください。 (例えば、浄土真宗は水をお供えしない など。) |
スポンサードリンク
①−3. お供え(お迎え団子、おちつき団子、送り団子 |
初盆・新盆、お盆のためにお団子を用意することがあります。 |
| お迎え団子 |
| お迎え団子とは 盆の入り・お盆の入りの13日にお供えする団子です。
宗派や地方によっては前日の12日からお供えすることもあります。 ●盆供(お盆のお供えもの)は日替わりで用意される風習があり、もともとは盆の入りの日(13日)にお供えするものが「お迎え団子」でしたが、現在ではお盆の期間中、同じものをお供えすることもあるようです。 ●お迎え団子の種類もさまざまです。 お迎え団子の名称で販売されているものには、あんこをまぶした団子、甘辛いたれをのせた団子、シンプルな白い団子などがあります。 |
| おちつき団子、お供え餅、お供え団子 |
落ち着き団子あるいはお供え持ち、お供え団子とはl,精霊様(おしょうらいさま)が滞在中の14〜15日にお供えするお供物です。
●盆の入りの「お迎え団子」、「盆明けの「送り団子」という名称に対し、精霊様の滞在中にお供えするものを「おちつき団子(落ち着き団子、落着き団子)」と呼ぶことがあります。 ●おちつき団子という名称で販売されている代表的なものには、おはぎがあります。 (注/おちつき団子という名称は、地方によっては使われないエリアがあります) ●京都ではお盆にお供えする白餅を「おけそく」「おけそくさん」と呼ぶようです。仏様へのお供え物を盛る器「華足(=けそく)」からきているようです。 ●お供え団子という名称で販売されている代表的なものは、白いシンプルなお団子です。ピラミッドの形に積み上げられたものをお供えすることもあります。 |
| 送り団子 |
送り団子とは盆の明けの16日にお供えする団子です。
宗派や地方によっては前日の15日からお供えすることもあります。 ●送り団子の名称で販売されているものには、シンプルな白い団子などがあります。 |
スポンサードリンク
①−4. その他の盆飾りやお供え |
お盆のために用意される飾りは、お供えの一種でもあります。主なものは以下の通りです。 |
| 1. 精霊棚(しょうりょうだな)…お盆の期間に、仏壇の前にしつらえます。お盆の期間中、ご位牌は仏壇から出して精霊棚に安置されます。詳細は初盆のページへ>>> |
| 2. 精霊馬(しょうりょううま)…お盆の期間に帰ってくる故人やご先祖様の乗り物として、なすやきゅうりで、馬や牛を作ります(なすの牛、きゅうりの馬)。詳細は初盆のページへ>>> |
| 3. 盆提灯 盆提灯は祖先の霊が提灯を目印にして戻って来られるように飾ると言われています。 お盆に使われる盆提灯には、白提灯と絵柄の入った提灯があります。 白提灯だけは初盆にのみ用い、軒先や玄関先などに飾ります。絵柄の付いた盆提灯は精霊棚の両脇に飾り、初盆以外のお盆にも用います。 ▼新盆・新盆には白提灯 初盆・新盆用には白提灯をかざります。白提灯は近親者から贈られることが多いようです。…詳細は初盆のページ「盆提灯」へ>>> |
| 4. 盆花 盆花とは、精霊棚に吊るす花をさします。代表的な盆花としてほおずき、蒲の穂、枝豆などが逆さに吊るされます。 精霊棚をしつらえない場合には、お盆のために花立てに盆花または故人がお好きだった花を飾ります。詳細は初盆のページへ>>> |
| ② その他の盆飾りやお供え |
| 上記以外のお供え、お供物、お供え物として 初盆・新盆の法要のために、遺族や親族、親戚、初盆・新盆に出席できない親族や友人などがお供え物を手配することがあります。 お菓子、果物、籠盛りの果物、お花などが代表的なお供物となります。 人気のあるお供物は次のページで紹介しています。>>> |
| ▼3. 初盆・新盆のお供え・お供え物・御供物として人気があるのは…次のページ |
| ▼4. お供え・お供物・御供物を送る場合…次のページ |
| ・手紙を添える場合…次のページ |
| ▼5. お返し、お礼…次のページ |
| ……………………………… |
|---|
| ※ 初盆・新盆のマナー・作法・流れなどは別ページへ>>> |
| ※ 初盆のお返し・浄土真宗の初盆などは別ページへ>>> |
スポンサードリンク